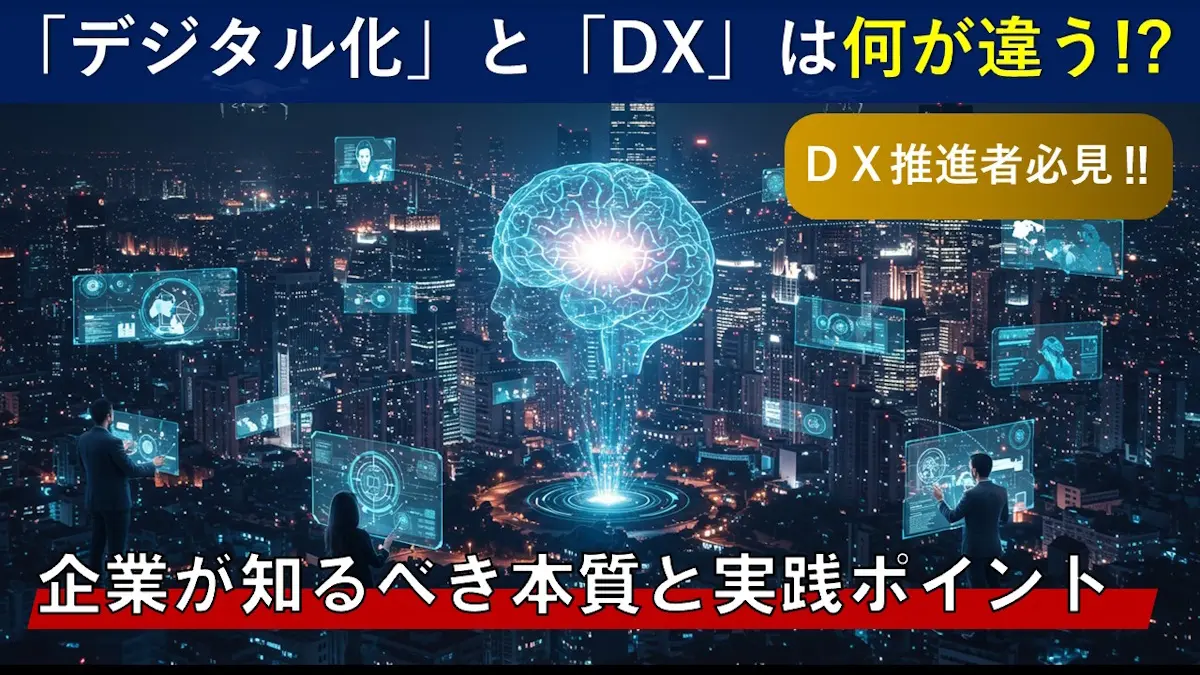
「デジタル化」と「DX」の違いとは? 企業が知るべき本質と実践ポイントを解説
最終更新日:2025/08/30
近年、ビジネスの世界で「デジタル化」や「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を頻繁に耳にするようになりました。
しかし、これらの言葉の意味を正確に理解し、その違いを明確に説明できるビジネスパーソンはまだ多くないかもしれません。
DXの推進が企業の競争力を左右する時代において、その本質を理解することは不可欠です。
今回は、「デジタル化」と「DX」の違いを明確にしながら、企業の担当者が知っておくべきDXの本質と、その推進における重要なポイントを紹介します。
「デジタル化」とは?
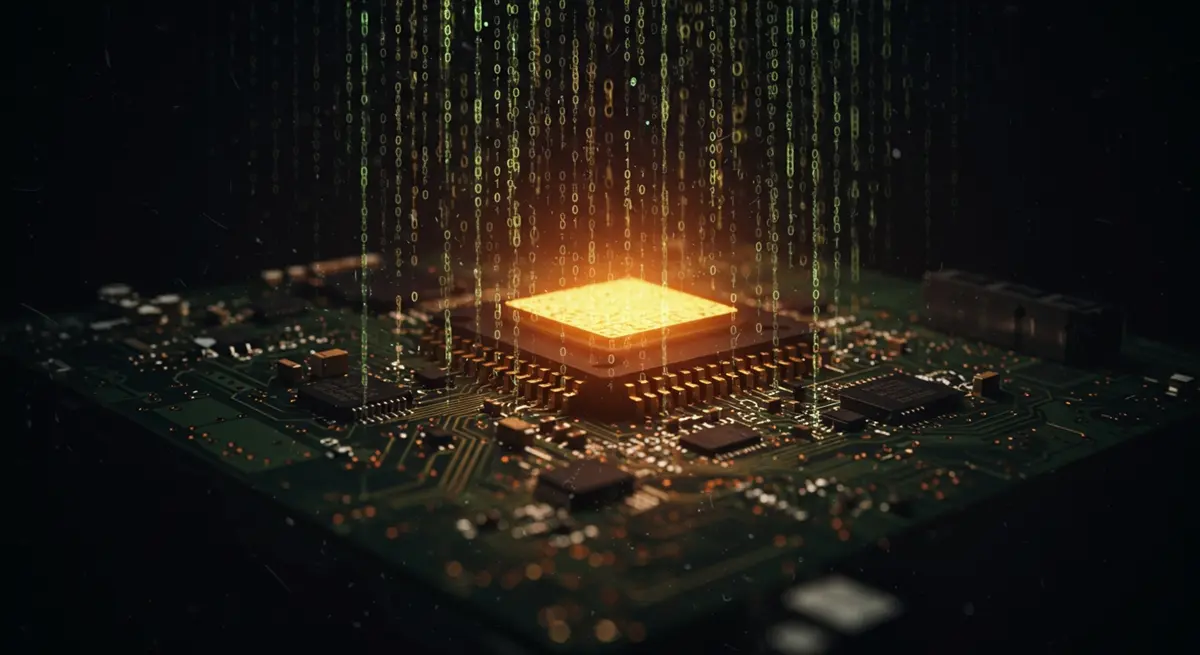
まず、「デジタル化」とは、既存のアナログな業務プロセスをデジタル技術に置き換えることで、業務の効率化や生産性の向上を目指す取り組みを指します。
あくまでも、現在の業務を主体とした改善活動です。
この「デジタル化」は、厳密には2つの段階に分けて捉えると、より理解が深まります。
ステップ1:デジタイゼーション
これは「アナログ情報のデジタルデータ化」を指します。個別の点的なデジタルへの置き換えです。
具体的には、「紙の書類をスキャンしてPDFにする」、「会議の音声を録音してデータとして保存する」、「紙のアンケート結果をExcelに入力する」などが挙げられます。
ステップ2:デジタライゼーション
これは「特定の業務プロセス全体のデジタル化」を指します。
デジタイゼーションによってデータ化された情報を活用し、業務フローを線としてデジタル化することです。
具体的には、「契約書を電子契約サービスに切り替え、申請から承認、保管までをオンラインで完結させる」、「経費精算をアプリで行い、申請から上長の承認、経理部門の処理までを一気通貫で行う」などが挙げられます。
身近な業務におけるデジタル化の具体例
コミュニケーション手段の進化は、この「デジタル化」の分かりやすい一例です。
かつてビジネスの主な手段だった電話やFAXが、電子メールやチャットツールに置き換わったことで、時間や場所の制約なく、迅速なコミュニケーションが可能になりました。
デジタル化が各業務領域でどのような変化をもたらすのか、具体的なシーンで見ていきましょう。
書類を管理する場面の例
書類管理の領域では、従来、紙の契約書をファイリングしてキャビネットで物理的に保管しており、押印のためだけに出社が必要になることも珍しくありませんでした。
これがデジタル化されると、書類はクラウド上で一元管理され、電子契約サービスを活用することで、場所を問わずに契約業務を完結させることが可能になります。
会議や情報共有の場面の例
会議や情報共有のあり方も大きく変わります。
以前は対面での会議が必須で、議事録は会議が終わった後に担当者がWordなどで作成し、メールで共有するのが一般的でした。
今ではWeb会議システムによって遠隔からの参加が当たり前になり、議事録も共同編集ツールを使えば会議中にリアルタイムで作成・共有できます。
営業活動の場面の例
営業活動においても、かつては紙の名刺や手帳で顧客情報を管理し、日報は手書きや個人のExcelファイルで報告されていました。
デジタル化後は、CRMやSFAといったツールで顧客情報が一元管理され、商談の履歴や進捗もチーム全体でリアルタイムに共有されるようになります。
経理や申請業務の場面の例
経理や申請業務では、紙の請求書や領収書を担当者が手で集計し、Excelへ手入力する作業が発生していました。
また、稟議書を印刷して関係者の間を物理的に回覧する「押印リレー」も行われていました。
これらは、会計ソフトが請求書発行から仕訳までを自動化し、ワークフローシステムがオンラインで申請から承認までを完結させることで、大幅に効率化されます。
このように、アナログで行っていた作業をデジタルに置き換えることがデジタル化の第一歩です。
この取り組みによって得られる「コスト削減」、「業務時間の短縮」、「人為的ミスの削減」、「情報共有の円滑化」といった効果は、企業の生産性を大きく向上させます。
そして最も重要なのは、デジタル化を進めることで、これまで活用されてこなかった様々なデータが企業に蓄積され始めるという点です。
この蓄積されたデータこそが、次のステップであるDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための、必要不可欠な土台となるのです。
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは?

一方、「DX」は、単なる業務効率化にとどまりません。
データやデジタル技術を駆使して、製品・サービス、ビジネスモデル、業務プロセス、そして組織や企業文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創出して持続的な競争上の優位性を確立することを目的とします。
これは、まさに「ビジネスの再定義」と言えるでしょう。
この「変革」が具体的に何を指すのか、企業の活動における主要な側面から見ていきましょう。
製品・サービスの変革
例として売り切りモデルからサービスモデルへの転換があげられます。
自動車メーカーが単に「車」という”モノ”を売るだけでなく、カーシェアリングやサブスクリプションといった「移動」という”コト(サービス)”を提供する。
このように、製品にデジタルを組み合わせて継続的な顧客接点と新たな収益源を生み出します。
ビジネスモデルの変革
例として、DVDレンタルからコンテンツ配信・制作への転換があげられます。
かつてのNetflixが物理的なDVDの郵送レンタル事業から、オンラインでの動画ストリーミングサービスへ、さらには独自のコンテンツを制作・配信する企業へとビジネスの根幹を変化させたのが典型例です。
市場の変化を捉え、収益構造そのものを変革します。
顧客体験(CX)の変革
例として、画一的な接点からパーソナライズされた体験への転換があげられます。
店舗での接客や画一的なDM送付だけでなく、顧客の購買履歴や行動データを分析し、一人ひとりに最適化された商品をオンラインで推薦したり、アプリを通じて特別な体験を提供したりします。
顧客とのあらゆる接点をデジタルで繋ぎ、満足度とロイヤリティを高めます。
組織・企業文化の変革
例として、トップダウン文化からデータドリブン・アジャイル文化への転換があげられます。
経験や勘に頼った意思決定から、データを根拠とした客観的な意思決定へ移行します。
また、部署間の壁を取り払い、迅速な試行錯誤を許容するアジャイルな文化を醸成しなければ、DXの推進は困難です。
これはDXの成否を分ける最も重要な要素とも言われます。
このように、DXとは、デジタル化を「手段」として活用し、ビジネスのあり方を根本から変える「目的」そのものなのです。
それは、例えるなら芋虫が蝶へと変態するようなものです。
単に芋虫が速く歩けるようになる(業務効率化)のではなく、蝶になって空を飛ぶという全く新しい能力を得る(新たな価値創造)ということなのです。
それがDXの本質であり、変化の激しい時代を企業が生き抜くための、不可欠な経営戦略と言えます。
多様な業界におけるDX事例

DXは特定の業界に限った話ではありません。
様々な業界で、企業がそれぞれの課題解決や新たな価値創造のためにDXを推進しています。
製造業の例
製造業の例として、トヨタ自動車の取り組みがあります。
トヨタ自動車では、材料開発においてAIとシミュレーション技術を活用し、従来1000工程以上かかっていたプロセスを約半分に短縮。
開発期間の大幅な効率化を実現しました。
小売業の例
小売業の例として、ニトリホールディングスの取り組みがあります。
ニトリホールディングスでは、データ活用の内製化を進め、顧客一人ひとりのニーズに合わせた商品開発や、天候・需要予測に基づく最適な店舗在庫の配置を実現しました。
金融業の例
金融業の例として、りそなホールディングスの取り組みがあります。
りそなホールディングスでは、スマートフォンアプリを起点とした顧客接点のデジタル化を推進し、非対面での取引を完結させるとともに、収集したデータを活用した新たな金融サービスの提供に繋げています。
建設業の例
建設業の例として、八千代エンジニヤリングの取り組みがあります。
八千代エンジニヤリングでは、AIを活用して河川のコンクリート護岸の劣化を自動判定するシステムを開発しました。
熟練技術者のノウハウをAIに継承し、インフラ点検の効率化と精度向上を実現しました。
DX推進に不可欠な3つの要素

DXを単なるスローガンで終わらせず、企業の成長エンジンへと昇華させるためには、互いに連携する次の3つの要素が不可欠です。
これらはどれか一つが欠けても、DXの成功はおぼつきません。
データドリブンな意思決定
経験や勘だけに頼るのではなく、収集・蓄積したデータを分析し、客観的な事実に基づいて意思決定を行う文化を醸成します。
しかし、単に「データを使いましょう」と号令をかけるだけでは不十分です。
そのためには、誰もがデータを活用できる次のような「民主化されたデータ基盤」の整備が前提となります。
その1:データの収集・統合
営業部門の顧客データ、マーケティング部門のWebサイトアクセス解析データ、製造部門の稼働データなど、各部署に散在しているデータを一元的に集約し、連携させる仕組みを構築します。
その2:データの可視化と分析
集約したデータを、専門家でなくても理解できるようグラフやダッシュボードで可視化するBIツールなどを導入します。
これにより、現場の担当者が自ら課題を発見し、改善アクションに繋げることが可能になります。
組織改革・企業文化の変革
DXは技術導入だけでは決して成し遂げられません。
むしろ、それを使いこなすための組織と文化の変革こそが、最も重要であり、最も困難な課題です。
その1:変化を恐れず挑戦を推奨する文化
DXの推進には試行錯誤がつきものです。
一度の失敗で担当者を責めるのではなく、挑戦そのものを評価し、失敗から学ぶことを推奨するフェイルファストの精神を経営層が明確に打ち出すことが重要です。
その2:部門間の壁の撤廃とアジャイルな体制
顧客に新たな価値を提供するためには、企画、開発、営業、マーケティングといった部門の垣根を越えた連携が不可欠です。
特定の課題解決のために部門横断型のチームを組成し、短期間で「計画→実行→評価→改善」のサイクルを回すアジャイルな働き方を導入することが求められます。
エコシステムの構築
変化の速い現代において、全ての技術やノウハウを自社だけで完結させようとする「自前主義」は、もはや限界を迎えています。
他社やスタートアップ、大学など、外部の組織が持つ優れた技術やアイデアと連携し、新たな価値を「共創」していく視点が不可欠です。
その1:スタートアップ連携
自社にない革新的な技術(AI、IoTなど)を持つスタートアップ企業に出資や業務提携を行い、スピーディーに新サービスを開発します。
その2:産学連携
大学の研究室などと共同で、次世代のコア技術となるような基礎研究に取り組みます。
その3:異業種連携
他業種の企業とデータを共有したり、共同で新たなプラットフォームを構築したりすることで、単独では生み出せなかった新しいビジネスモデルを創出します。
オープンイノベーションを通じて、自社だけでは生み出せないアイデアや技術を積極的に取り込むことで、DXの可能性は飛躍的に拡大します。
DX推進を阻む「4つの壁」とその乗り越え方

多くの企業がDXを推進する過程で、共通の課題、いわば「壁」に直面します。
ここでは、代表的な4つの壁と、それを乗り越えるための具体的な解決策をご紹介します。
1つ目の壁:経営層のビジョン・コミットメント不足
DXが失敗する最大の要因とも言われるのが、経営層の関与の薄さです。
DXを単なるIT部門の取り組みやコスト削減策と捉えていると、全社的な協力が得られず、プロジェクトは頓挫してしまいます。
解決策としては、次のようなものがあります。
解決策その1:経営者自らが「最高責任者」となる
経営層が「なぜDXをやるのか」、「DXによって会社をどう変えたいのか」という目的とビジョンを、自らの言葉で繰り返し全社に発信します。
解決策その2:具体的な投資と権限移譲
「DX推進室」のような専門部署を設置し、十分な予算と、部門間の調整を行える強い権限を与えます。
経営会議でDXの進捗を最重要アジェンダとして定期的に議論することも、コミットメントを示す上で不可欠です。
解決策その3:評価制度との連動
役員や管理職の評価項目に「DXへの貢献度」を組み込むことで、組織全体がDXを「自分ごと」として捉える文化を醸成します。
2つ目の壁:DX人材の圧倒的な不足
いざDXを進めようとしても、「何から手をつければいいかわかる人がいない」、「データを分析できる人材がいない」という問題に直面します。
専門人材の採用は競争が激しく、外部からの採用だけに頼るのは困難です。
解決策としては、次のようなものがあります。
解決策その1:必要な人材像の明確化
一口にDX人材と言っても、プロジェクトを牽引するリーダー、データを分析するサイエンティスト、システムを構築するエンジニアなど役割は様々です。
まずは自社のDX戦略に必要な人材を定義することが第一歩です。
解決策その2:外部知見の戦略的活用と内製化の両立
初期段階では、外部の専門家やコンサルタントの知見を借りてプロジェクトを推進しつつ、そのノウハウを自社の社員が吸収できる体制を整えます。
丸投げは避け、将来的な内製化を目指します。
解決策その3:全社的なリスキリング(学び直し)の推進
IT部門だけでなく、事業部門の従業員がデジタルスキルを習得することが重要です。
オンライン学習プログラムの導入や専門知識が少なくてもアプリ開発ができる、ローコード・ノーコードツールの活用を促し、全社員のデジタルリテラシーを底上げします。
3つ目の壁:既存システム(レガシーシステム)の存在
長年にわたって部署ごとに最適化され、複雑に絡み合った既存システムは、DX推進における「技術的負債」となります。
データが各システムに分散して連携できない、新しいデジタル技術と接続できないといった問題を引き起こします。
解決策としては、次のようなものがあります。
解決策:現状の可視化と段階的な刷新計画
まずは自社のシステム全体を棚卸しし、どのシステムがどのような課題を抱えているかを可視化します。
全てを一度に刷新するのは現実的ではないため、「データを連携させるためのAPIを整備する」、「特に足かせとなっているシステムから優先的に刷新する」といった段階的な計画を立てることが重要です。
4つ目の壁:組織・部門間の壁と現場の抵抗
DXは、特定の部門だけでなく全社で取り組むべき活動です。
しかし、実際には「それはIT部門の仕事だ」、「新しいやり方は面倒だ」といった部門間の壁や、変化に対する現場の心理的な抵抗が発生しがちです。
解決策その1:「小さな成功体験(スモールサクセス)」の創出と共有
最初から大規模なプロジェクトを目指すのではなく、特定の部署や業務で成果が出やすいテーマを選び、まずは「小さな成功体験」を創出します。
「新しいツールのおかげで残業が月10時間減った」のような具体的なメリットを成功事例として全社に共有し、DXへの期待感を醸成します。
解決策その2:現場を巻き込む体制づくり
各部門からDXに関心のあるメンバーを選出して部門横断の専門チームを設置し、現場の課題やニーズを吸い上げながら推進します。
トップダウンの指示だけでなく、現場の意見を尊重し、一緒に作り上げていく姿勢が抵抗を和らげます。
DX時代に求められる「変革型リーダーシップ」とは

DXの成否は、技術や戦略以上に、リーダーの存在が大きく左右します。
従来の、計画通りに業務を遂行する「管理型リーダーシップ」だけでは、不確実で変化の激しいDX時代を乗り切ることはできません。
DX時代のリーダーには、組織を未来へ導くための「変革型リーダーシップ」が求められます。
具体的には、次の4つの役割が不可欠です。
ビジョンを「物語る」力
DXによって何を実現したいのか、単に目標を掲げるだけでは人の心は動きません。
リーダーは、なぜ今変革が必要なのか、DXによってどのような未来が待っているのかを、情熱と一貫性をもって語る「最高物語責任者」であるべきです。
「Why」から語る
「AIを導入する」といった「What(何を)」からではなく、「AIを活用し、社員を単純作業から解放することで、お客様への価値提供という創造的な仕事に集中できる時間を作る」といった「Why(なぜ)」から語り、共感を呼び起こします。
繰り返し発信する
全社会議、部門会議、社内報、日々のコミュニケーションなど、あらゆる場面でビジョンに触れ、組織の隅々まで浸透させます。
変革の「盾」となり推進する力
変革には、既存のやり方への固執や、失敗への恐れといった「抵抗」が必ず伴います。
リーダーは、その抵抗に臆することなく強い意志で変革をリードすると同時に、挑戦するチームを社内の抵抗から守る「盾」となる必要があります。
大胆な意思決定
全社最適の視点から、時には聖域とされてきた業務プロセスや組織構造の見直しなど、痛みを伴う大胆な意思決定を下します。
挑戦を許容する文化づくり
「失敗は責められるものではなく、貴重な学習機会である」というメッセージを明確に発信し、社員が安心して挑戦できる「心理的安全性」を確保します。
DX推進チームが既存事業部門からの批判に晒された際には、自らが矢面に立って守ります。
「対話」を生み出すコミュニケーション能力
トップダウンで指示を出すだけの一方通行のコミュニケーションでは、現場の知恵や熱意を引き出すことはできません。
リーダーは、組織の声に真摯に耳を傾ける役割を担わなければなりません。
双方向の対話を促す
定期的に現場の従業員と直接対話する場を設け、DXへの不安や疑問、アイデアを率直に聞きます。
透明性の確保
成功事例だけでなく、うまくいっていないことや課題もオープンに共有することで、組織との信頼関係を築き、一体感を醸成します。
自ら学び「アジャイル」を体現する姿勢
DXに完璧な正解や計画は存在しません。
リーダー自身が変化に柔軟に対応するアジャイルな姿勢を自ら体現することが、組織全体の変革マインドを育みます。
アンラーニング(学びほぐし)
過去の成功体験に固執せず、時には自らのやり方を否定し、新しい知識やスキルを謙虚に学ぶ姿勢を示します。
「やってみよう」の精神
完璧な計画を待つのではなく、「まずは小さく試してみよう」と促し、試行錯誤の中から学びを得て次のアクションに繋げていくサイクルを自ら実践します。
DXの成功を測るKPIの設定

DXは大規模な投資を伴うため、その効果を客観的に測定し、改善に繋げていくことが不可欠です。
そのために重要なのが、KPIという重要業績評価指標の設定です。
KPI設定のポイント
KPI(重要業績評価指標)を設定する際にとても役立つ考え方として、「SMART」というフレームワークがあります。
これは、効果的な目標設定のための5つの要素の頭文字をとったものです。
Sは「具体的(Specific)」です。
誰が見ても同じように理解できる、曖昧さのない具体的な指標にしましょう。
Mは「測定可能(Measurable)」です。
定量的に測れる指標である必要があります。
たとえば「売上を上げる」ではなく、「売上を100万円増やす」のように、数字で測れるようにするのです。
Aは「達成可能(Achievable)」です。
現実的に達成できる目標にすることが重要です。
あまりにも高すぎる目標は、チームのモチベーションを下げてしまう可能性があります。
Rは「関連性(Relevant)」です。
設定するKPIが、最終目標であるKGI(重要目標達成指標)としっかり結びついているか確認しましょう。
KGI達成に直接貢献しないKPIは意味がありません。
Tは「期限(Time-bound)」です。
いつまでに達成するのか、明確な期限を定めることが大切です。
期限があるからこそ、計画的に行動できます。
このようにKGIを達成するための中間指標として、KPIをSMARTの観点で設定し、定期的に進捗を確認しながら改善を繰り返すことが、成功への鍵となります。
まとめ

今回は、「デジタル化」と「DX」の違い、そしてDXを成功に導くためのポイントを紹介しました。
「デジタル化」は、既存業務の効率化・生産性向上を目指す「手段」です。
「DX」は、ビジネスモデルの変革を通じて、新たな価値創造を目指す「目的」です。
両者は目的こそ異なりますが、無関係ではありません。
多くの場合、まずはデジタル化によって業務を効率化し、そこで得られた人材、時間、コストなどを新たな価値創出の取り組みに向けることが、現実的な進め方と言え、そのために経営層から現場までが一丸となって取り組む体制を構築することが何よりも重要です。



