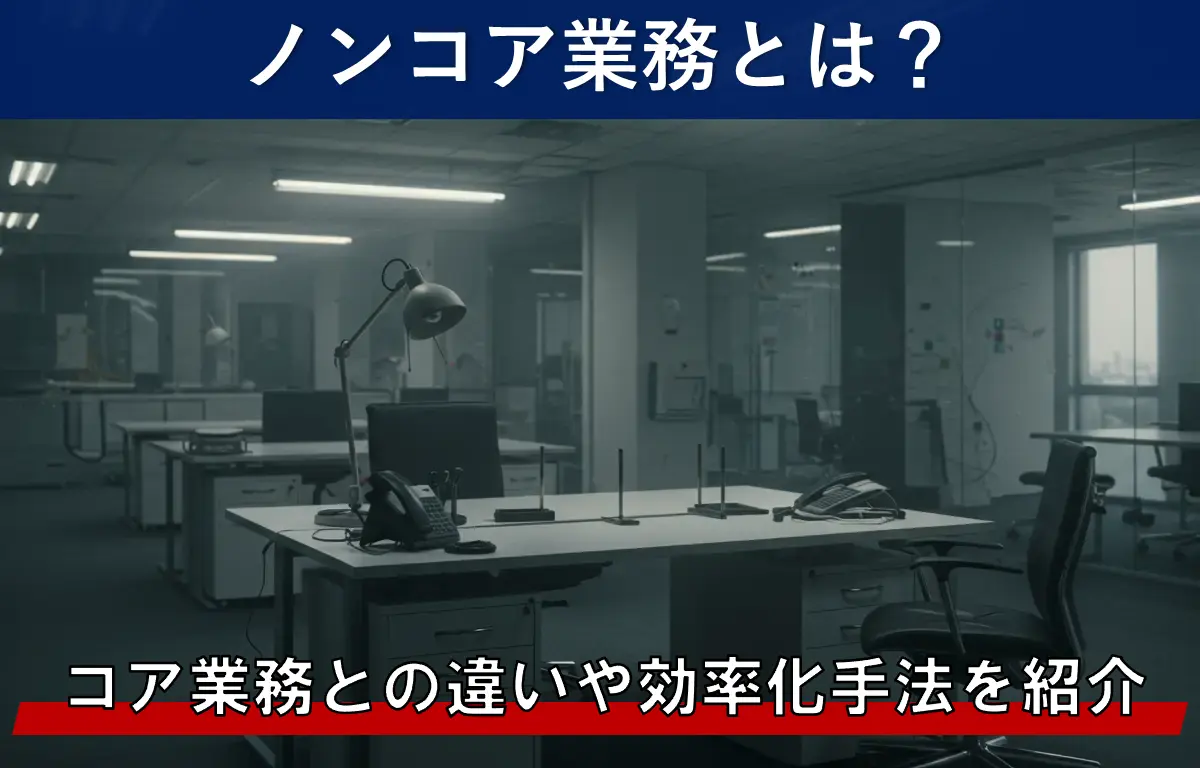
ノンコア業務とは?コア業務との違いや効率化手法を紹介
最終更新日:2025/09/09
なぜ「ノンコア業務」の見直しが企業の成長を左右するのか

企業の活動は、顧客に直接的な価値を提供し、収益の源泉となる「コア業務」と、そのコア業務を円滑に進めるために不可欠な、多種多様な「ノンコア業務」によって成り立っています。
製品の企画・開発や、顧客への直接的な営業活動がコア業務の代表例だとすれば、経理、人事、総務、情報システムの運用といったバックオフィス業務の多くは、ノンコア業務に分類されます。
これまで、多くの日本企業では、これらのノンコア業務も「自社の業務は、自社の社員で完結させる」という、いわゆる自前主義のもと、社内で抱えることが一般的でした。
しかし、労働人口の減少が深刻化し、市場の不確実性が増す現代において、この自前主義は、企業の成長を阻害する大きな足かせとなりつつあります。
限られた人材という貴重な経営資源を、利益に直結しないノンコア業務にまで、これまで通りに投下し続けることは、果たして賢明な判断と言えるのでしょうか。
むしろ、ノンコア業務に多くの時間や人材を割かれた結果、本来注力すべきコア業務への投資が疎かになり、企業の競争力そのものが低下してしまう、という本末転倒の事態に陥っているケースも少なくありません。
このような経営課題を解決するための鍵として、今、大きな注目を集めているのが、「ノンコア業務」の戦略的な見直しです。
自社の業務を「コア業務」と「ノンコア業務」に明確に切り分け、ノンコア業務については、ITツールの活用による自動化・効率化や、外部の専門家の活用を積極的に進める。
そして、それによって創出された社内時間や人材を、企業の競争力の源泉であるコア業務へと再配分する。
この選択と集中こそが、変化の激しい時代を生き抜くための、現代企業に必須の経営戦略なのです。
しかし、「ノンコア業務は重要ではない業務だ」と考えるのは、早計です。
ノンコア業務は、企業の根幹を支える重要な土台であり、その品質や効率性は、組織全体の生産性に大きな影響を与えます。
したがって、その見直しは、単なるコスト削減を目的とした、短期的な視点で行うべきではありません。
今回は、「ノンコア業務とは何か?」という基本的な定義から、その見極め方、そしてノンコア業務の効率化・最適化を実現するための手法を紹介します。
ノンコア業務とは何か?コア業務との違いを理解する

ノンコア業務の見直しを始めるにあたり、まず不可欠なのが、「何がコア業務で、何がノンコア業務か」を、自社の状況に合わせて正しく定義することです。
この切り分けが曖昧なままでは、その後の戦略も的を射たものにはなりません。
コア業務の定義
コア業務とは、企業の「コアコンピタンス(競合他社には真似のできない、自社ならではの中核的な強み)」を源泉とし、顧客に直接的な価値を提供し、収益を生み出す、事業の根幹をなす活動を指します。
言い換えれば、「その業務がなくなると、企業の存在価値そのものが揺らぐ」ような、事業の心臓部と言えるでしょう。
コア業務は、企業が市場で勝ち残っていくための、競争優位性の源泉そのものです。
したがって、これらの業務には、社内の最も優秀な人材や、潤沢な予算といった、最良の経営資源を優先的に投下すべきです。
コア業務の具体例
・製造業: 新製品の研究開発、基幹技術の開発、ブランド戦略の立案、サプライチェーンの中核管理
・小売業: 商品の仕入れ、店舗コンセプトの企画、独自の接客サービスの開発、マーケティング戦略の策定
・ITサービス業: ソフトウェアの基本設計・開発、独自のアルゴリズム開発、コンサルティングサービスの提供、インフラの根幹設計
ノンコア業務の定義
ノンコア業務とは、事業を運営する上で不可欠ではあるものの、それ自体が直接的に収益を生み出すわけではなく、他社と比較しての競争優位性の源泉とはなりにくい、支援的・補助的な業務を指します。
これらの業務は、もちろん重要ではないわけではありません。
むしろ、ノンコア業務が滞れば、コア業務の遂行にも支障をきたすため、企業の土台を支える重要な役割を担っています。
しかし、その業務の遂行方法が、必ずしも自社独自のものである必要はなく、多くの場合は業界標準のプロセスが存在します。
ノンコア業務の具体例
・経理・財務: 伝票処理、記帳代行、請求書発行、経費精算、給与計算
・人事・労務: 社会保険・労働保険の手続き、勤怠管理、採用活動の一部(応募者管理など)、社員データ管理
・総務: 備品管理・発注、受付・電話対応、文書管理、オフィス環境の整備
・情報システム: ヘルプデスク、PCのセットアップ、定型的なシステム運用・監視
・営業: 営業資料の作成、データ入力、アポイント獲得のための電話営業
コア業務とノンコア業務の境界線は変化する
ここで重要なのは、コア業務とノンコア業務の境界線は、固定的ではなく、企業の事業戦略や、市場環境、技術の進化によって、常に変化しうる、ということです。
例えば、かつては多くの企業にとってノンコア業務であった「Webサイトの運営」も、EC事業を主力とする企業にとっては、顧客との重要な接点であり、売上を左右する、まぎれもない「コア業務」となります。
また、AI技術の進化により、これまで専門家のコア業務とされてきたデータ分析の一部が、自動化可能なノンコア業務へと変化していく可能性もあります。
したがって、「我々にとってのコア業務とは何か?」という問いは、経営層や各部門のリーダーが、定期的に自問し、再定義し続けなければならない、極めて重要な検討事項なのです。
なぜノンコア業務の見直しが重要なのか

ノンコア業務を特定し、その在り方を見直すことは、現代企業にとって、どのような戦略的な意味を持つのでしょうか。
その重要性は、単なる業務効率化にとどまらず、企業の成長と変革を促す、より深い次元にあります。
経営資源の「選択と集中」の実現
企業が保有する経営資源、すなわち「ヒト、モノ、カネ、情報」は、有限です。
これらの限られた資源を、すべての業務に等しく配分していては、競争が激化する市場で勝ち抜くことはできません。
ノンコア業務を効率化・最適化することで、そこに投下されていた人材、予算、時間を解放し、企業の未来を創るコア業務へと再投資する。
この経営資源の「選択と集中」こそが、ノンコア業務を見直す最大の目的です。
例えば、経理部門の優秀な社員が、日々の伝票処理に多くの時間を費やしているとしたら、それは企業にとって大きな機会損失です。
その定型業務を外部委託やITツールで代替し、その社員が、財務分析や経営企画といった、より高度なコア業務に挑戦できる環境を整えることが、企業全体の競争力を高めることに繋がります。
組織全体の生産性向上
ノンコア業務には、定型的で反復的な作業が多く含まれており、これらは、しばしば業務の障害や制約となり、組織全体の生産性を低下させる原因となります。
これらの業務を、外部の専門家やITツールに任せることで、業務プロセス全体が標準化・効率化され、処理速度と正確性が飛躍的に向上します。
これにより、コア業務に従事する社員も、必要な情報を迅速かつ正確に入手できるようになり、自らの業務をより円滑に進めることができるようになります。
ノンコア業務の効率化は、バックオフィス部門だけの問題ではなく、組織全体の質を底上げする効果を持つのです。
従業員満足度の向上と人材育成
価値の低い単純作業や、キャリアの成長に繋がりにくい定型業務は、従業員のやる気を低下させる大きな要因となります。
特に、高い能力と成長意欲を持つ優秀な人材ほど、そのような業務に閉塞感を覚え、より挑戦的な機会を求めて、社外に目を向けてしまいがちです。
ノンコア業務を外部化・自動化することは、従業員を、こうした単純作業から解放し、彼らが自らの専門性や創造性を発揮できる、より付加価値の高いコア業務へと挑戦する機会を創出します。
自らの仕事が、会社の成長に直接貢献しているという実感は、従業員の満足度を大きく向上させ、優秀な人材の定着にも繋がります。
外部環境の変化への迅速な対応
市場のニーズや、法規制、技術トレンドは、常に変化しています。
ノンコア業務を専門性の高い外部パートナーに委託することで、これらの外部環境の変化に、自社だけで対応するよりも、迅速かつ的確に対応することが可能になります。
例えば、頻繁に改正される税制や労働法規への対応、あるいは、日々巧妙化するサイバーセキュリティへの対策など、専門的な知見が必要な領域において、常に最新の情報とノウハウを持つ専門家の力を活用できることは、企業のリスク管理能力と変化対応能力を大きく高めます。
ノンコア業務を効率化・最適化する手法

ノンコア業務を見直す重要性を理解したところで、次は、それを具体的に、どのように効率化・最適化していくか、という実践的な手法について見ていきましょう。
代表的な手法として、次の3つが挙げられます。
【手法1】BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の活用
これは、ノンコア業務を、業務プロセスごと外部の専門事業者に委託する手法です。
単なる作業の代行ではなく、業務の企画・設計から、実行、改善までを包括的に任せることが特徴です。
BPOのメリット
・コスト削減: 専門事業者の規模の経済や効率化ノウハウにより、自社で行うよりもコストを抑えられる場合が多いです。
・品質向上: プロフェッショナルによる高品質で安定した業務遂行が期待できます。
・コア業務への集中: 社員をノンコア業務から解放し、コア業務に専念させることができます。
BPOに適した業務
・給与計算、経理処理、コールセンター業務など、専門性が高く、かつ定型的な業務プロセス。
【手法2】ITツール・SaaSの導入による自動化・効率化
近年、クラウドベースで提供される安価で高機能なSaaS(Software as a Service)が、様々な業務領域で登場しています。
これらのITツールを導入することで、これまで手作業で行っていたノンコア業務を、自動化・効率化することが可能です。
ITツール導入のメリット
・業務効率の大幅な向上: 手作業によるミスをなくし、処理速度を飛躍的に向上させます。
・情報の一元管理と可視化: 業務に関する情報が一元化され、リアルタイムでの状況把握が可能になります。
・リモートワークへの対応: クラウドベースのツールであれば、場所を選ばずに業務を遂行できます。
ITツール導入に適した業務
・経費精算: 経費精算システムを導入し、申請から承認、支払いまでのプロセスを電子化・自動化する。
・勤怠管理: クラウド型勤怠管理システムを導入し、打刻から給与計算ソフトへの連携までを自動化する。
・採用管理: ATS(採用管理システム)を導入し、応募者の情報管理や、面接日程の調整を効率化する。
【手法3】シェアードサービスの設立
これは、グループ経営を行っている大企業でよく見られる手法です。
グループ各社に分散している、経理、人事、総務といった間接部門の機能を、一箇所に集約し、専門の子会社(シェアードサービスセンター)として独立させるアプローチです。
シェアードサービスのメリット
・グループ全体の業務標準化と効率化: グループ内でバラバラだった業務プロセスを標準化し、システムを統一することで、全体の効率が向上します。
・専門人材の育成: 特定の業務領域に特化した専門家集団を育成することができます。
・ガバナンスの強化: グループ全体の業務状況を可視化し、内部統制を強化しやすくなります。
シェアードサービス化に適した業務
・グループ各社で共通して発生する、定型的かつ大量の間接業務。
これらの手法は、排他的なものではありません。
「この業務はBPOを活用し、こちらの業務はSaaSを導入して内製化を維持する」といったように、業務の特性や、自社の戦略に応じて、これらの手法を戦略的に組み合わせていくことが、ノンコア業務改革を成功させる鍵となります。
ノンコア業務の見直しを成功させるためのステップ

ノンコア業務の見直しは、全社的なプロジェクトとして、計画的に進める必要があります。
ここでは、そのための5つのステップを紹介します。
【ステップ1】現状の業務プロセスの「可視化」
改革の第一歩は、現状を正確に把握することから始まります。
まず、対象となる業務について、「誰が」、「いつ」、「何を」、「どのように」行っているのか、その一連の流れを、フローチャートなどを用いて、第三者が見ても分かるように「可視化」します。
このプロセスを通じて、これまで暗黙知であった業務の手順や、特定の個人に依存している「属人化」した業務、そして、非効率な「ムリ・ムダ・ムラ」が潜んでいる箇所が明らかになります。
【ステップ2】業務の「棚卸し」と「仕分け」
可視化された業務の一つ一つについて、その業務が「コア業務」なのか、「ノンコア業務」なのかを仕分けしていきます。
この「棚卸し」と「仕分け」の作業は、経営層や各部門の責任者が集まり、全社的な視点で行うことが重要です。
「この業務は、本当に我々の競争優位性に繋がっているか?」、「この業務は、他社に任せることができないか?」といった問いを、徹底的に議論します。
【ステップ3】最適な効率化・最適化手法の選定
ノンコア業務と仕分けされた業務について、それぞれに最適な効率化・最適化の手法(BPO、ITツール導入、シェアードサービスなど)を検討し、選定します。
その際、コスト、品質、セキュリティ、導入にかかる期間といった、複数の評価軸で比較検討することが重要です。
例えば、業務量がそれほど多くなく、定型的な業務であれば、安価なSaaSの導入が適しているかもしれません。
一方で、専門性が高く、かつ業務量が大きい業務であれば、BPOベンダーに委託する方が、高い費用対効果が期待できるでしょう。
【ステップ4】導入計画の策定と実行
導入する手法が決まったら、具体的な実行計画を策定します。
・導入体制の構築: プロジェクトの責任者とメンバーを明確にし、社内の関連部署との連携体制を構築します。
・目標設定: 「いつまでに」、「どのような状態」を目指すのか、具体的なスケジュールと、定量的・定性的な目標(KPI)を設定します。
・パートナー選定: BPOやSaaSを導入する場合は、複数のベンダーを比較検討し、自社の要件に最も合致したパートナーを選定します。
・パイロット導入(スモールスタート): 全社展開の前に、特定の部署や業務に限定して試験的に導入し、効果や課題を検証する「パイロット導入」を行うことが、リスクを低減する上で有効です。
【ステップ5】効果測定と継続的な改善(PDCA)
ノンコア業務の見直しは、一度導入して終わりではありません。
導入後に、当初設定した目標(KPI)が達成されているかを、定期的に測定・評価し、改善を続けていくPDCAサイクルを回し続けることが不可欠です。
市場環境や、社内の状況は常に変化します。
BPOベンダーとの定例会や、ITツールの利用状況の分析を通じて、常に業務プロセスの最適化を図り、変化に対応していく姿勢が、ノンコア業務改革の成果を、持続的なものにします。
ノンコア業務の見直しは、未来への投資である

ノンコア業務は、企業の日常を支える、縁の下の力持ちのような存在です。
その重要性ゆえに、私たちは、その業務が「これまで通りのやり方」で、非効率なまま行われていることに、気づきにくいのかもしれません。
しかし、変化の時代において、「これまで通り」は、もはや緩やかな衰退を意味します。
ノンコア業務の見直しは、単なるコスト削減のための、後ろ向きなリストラクチャリングではありません。
それは、自社の真の強み(コアコンピタンス)は何かを再定義し、そこに経営資源を集中させることで、企業の未来を創造するための、極めて戦略的で、前向きな「投資」です。
この改革は、従業員一人ひとりにとっても、大きなチャンスとなり得ます。
価値の低い単純作業から解放され、自らの専門性や創造性を、企業の成長に直結するコア業務で発揮できること。
それは、働くことの喜びと、キャリアの可能性を、大きく広げることに繋がるはずです。
あなたの会社では、貴重な「人財」が、本当に輝ける場所で、その能力を最大限に発揮できているでしょうか。
ノンコア業務という、一見地味に見える領域にこそ、その大きな可能性を解き放つ、重要な鍵が隠されています。
まずは、自社の足元を見つめ直し、業務を可視化することから、始めてみてはいかがでしょうか。



