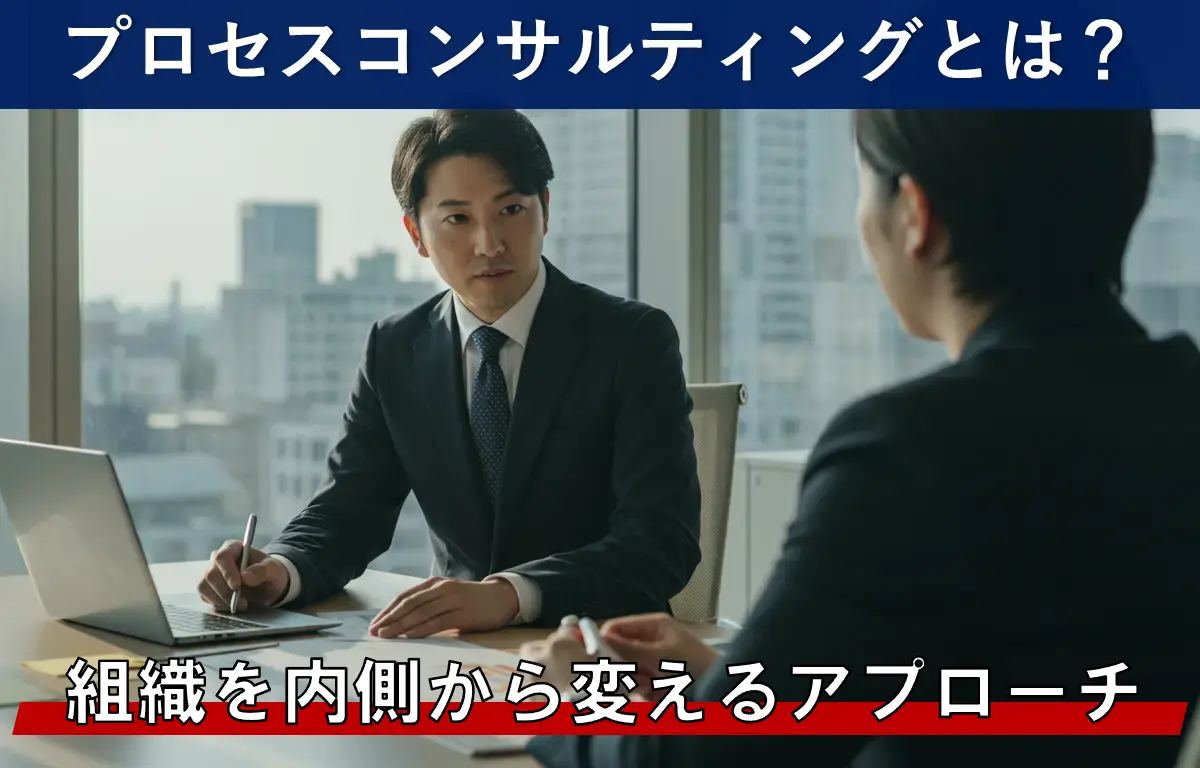
プロセスコンサルティングとは?組織を内側から変えるアプローチを紹介
最終更新日:2025/09/09
プロセスコンサルティングとは?

現代のビジネス環境は、予測不可能な変化と複雑性の増大に常に晒されています。
このような状況下で企業が持続的に成長し、競争優位性を維持するためには、外部環境の変化に迅速に対応できる、しなやかで自律的な組織能力が不可欠です。
しかし、多くの組織では、「言われたことしかやらない」、「部門間の連携が悪い」、「新しい挑戦が生まれない」といった、いわゆる「組織の病」に悩まされています。
こうした根深い問題を、外部の専門家が一時的に解決策を提示するだけでは、根本的な解決には至りません。
なぜなら、問題の本質は組織の「中」にあり、そこにいる人々自身が問題に気づき、自ら解決していく力を身につけない限り、同じ問題が再発してしまうからです。
ここで注目されるのが、「プロセスコンサルティング」というアプローチです。
プロセスコンサルティングは、組織開発の父とも呼ばれるエドガー・シャイン氏によって提唱された、コンサルティングの一つの形態です。
従来のコンサルティングが、クライアントの抱える特定の問題に対して、専門家として「答え(コンテンツ)」を提供することを主目的とするのに対し、プロセスコンサルティングは、クライアントが自ら問題解決のプロセスを学び、組織自身が自己診断能力と問題解決能力を高めていくことを支援することに主眼を置きます。
コンサルタントは「答えを教える専門家」ではなく、クライアントが問題解決のプロセスを効果的に進められるように支援する「触媒」や「ファシリテーター」としての役割を担います。
つまり、魚を与えるのではなく、「魚の釣り方」を教え、さらには「自分たちで新しい漁場を見つけ、新しい漁法を開発できる」ようになることを目指すアプローチなのです。
今回は、このプロセスコンサルティングの核心的な考え方から、従来型コンサルティングとの違い、導入プロセス、そしてそれが組織にもたらす真の価値までを紹介していきます。
従来型コンサルティングとの根本的な違い

プロセスコンサルティングの本質を理解するためには、一般的にイメージされる「専門家型」や「医者・患者型」と呼ばれる従来型のコンサルティングとの違いを明確にすることが有効です。
両者の間には、問題の捉え方、コンサルタントとクライアントの関係性、そして最終的なゴール設定において、根本的な思想の違いが存在します。
コンテンツ提供型(専門家型)コンサルティング
これは、クライアントが特定分野の知識や情報を求めている場合に有効なアプローチです。
例えば、最新の市場データ、特定の技術に関する専門知識、法規制に関する情報などをコンサルタントが提供します。
コンサルタントは「情報の提供者」であり、クライアントは「情報の受領者」という明確な役割分担があります。
問題は「情報の不足」であり、その解決策は「正しい情報の提供」となります。
医者・患者型コンサルティング
このモデルでは、コンサルタントは組織を診断し、問題箇所を特定し、処方箋(解決策)を提示する「医者」の役割を果たします。
クライアントは自覚症状を持つ「患者」として、医者の診断と処方を受け入れ、実行することが期待されます。
戦略コンサルティングや業務改革コンサルティングの多くがこのモデルに分類されます。
問題は組織内部の「病気」であり、その解決は外部の専門家による「手術」や「投薬」に例えられます。
このアプローチは、組織が自力で問題を発見・解決できない場合に迅速な効果を発揮することがあります。
プロセスコンサルティング
これら二つのモデルとは対照的に、プロセスコンサルティングは、「問題の所有者はあくまでクライアントである」という前提に立ちます。
コンサルタントは、クライアントが自身の問題を正しく診断し、解決策を自ら考え出し、実行していく、その一連の「プロセス」が円滑に進むように支援します。
コンサルタントは、会議の進め方、人間関係のダイナミクス、コミュニケーションのパターンなど、組織内で起こっている「プロセス」に焦点を当て、クライアント自身に気づきを促します。
例えば、会議で誰も発言しないという問題があった場合、「医者・患者型」では「発言を促すルールを作りましょう」と提案するかもしれません。
しかし、プロセスコンサルティングでは、「なぜ誰も発言しないのでしょうか?」、「この沈黙は何を意味しているのでしょうか?」と問いかけることで、メンバー自身がその背後にある心理的な不安や信頼関係の欠如といった根本原因に気づき、自ら解決策を見出すことを支援します。
このアプローチは、組織の自律性と学習能力を高め、長期的な組織変革を目指すものです。
プロセスコンサルティングの10の基本原則

エドガー・シャイン氏は、プロセスコンサルタントが持つべき心構えとして、10の基本原則を提唱しています。
これらの原則は、クライアントとの間に真の信頼関係を築き、効果的な支援を行うための羅針盤となります。
【原則1】常にクライアントを助けようとすること
コンサルタントの全ての行動は、クライアントの利益に繋がるという純粋な動機に基づいている必要があります。
【原則2】常に現実と接していること
クライアントの組織で現実に起こっていること、人々が感じていることに常に関心を持ち、そこから支援を始めなければなりません。
【原則3】自分の無知に気づくこと
コンサルタントは、クライアントの組織文化や人間関係、仕事の具体的な内容について、最初は何も知らない「無知」な状態であることを自覚し、謙虚に学ぶ姿勢を持つ必要があります。
【原則4】すべての行動が介入である
コンサルタントの存在そのもの、発する言葉、質問、沈黙でさえも、クライアントの組織に何らかの影響を与える「介入」であることを認識し、その影響に責任を持たなければなりません。
【原則5】問題を所有し、解決するのはクライアントである
コンサルタントがクライアントの問題を背負い込むことはできません。
問題のオーナーシップは常クライアントにあり、コンサルタントはその支援者であるという役割分担を明確にする必要があります。
【原則6】流れに身を任せること
クライアントの状況や関心事は常に変化します。
事前に立てた計画に固執するのではなく、その時々のクライアントのエネルギーや関心の流れに柔軟に対応することが重要です。
【原則7】タイミングがすべてである
どれだけ的確な指摘や提案であっても、クライアントがそれを受け入れる準備ができていなければ、効果はありません。
介入のタイミングを見極めることが、極めて重要です。
【原則8】建設的な対抗介入で、学習の機会を捉えること
クライアントが抵抗を示したり、非協力的な態度を取ったりした場合、それは組織の重要な側面を学ぶ機会となり得ます。
その抵抗の背後にあるものを探求し、クライアントに気づきを促すような、建設的な介入を行うことが求められます。
【原則9】すべてのことに答えがあるとは限らない。間違いは必ず起こる
コンサルタントも完璧ではありません。
自分の間違いを素直に認め、そこから学ぶ姿勢が、クライアントとの信頼関係を深めます。
【原則10】問題を共有し、リスクを引き受けること
最終的な責任はクライアントにありますが、コンサルティングのプロセスで生じる困難やリスクは、クライアントと共有し、共に乗り越えていくパートナーとしての姿勢が不可欠です。
プロセスコンサルティングの具体的な導入プロセス

プロセスコンサルティングは、通常、次のような段階を経て進められます。
それぞれの段階で、コンサルタントとクライアントは密接に連携し、対話を重ねながら関係性を深めていきます。
【第1段階】初期接触と関係構築
クライアントが何らかの問題意識を持ってコンサルタントに接触することから始まります。
この段階で最も重要なのは、クライアントが本当に助けを求めているのか、そしてコンサルタントがその支援に適しているのかを見極めることです。
契約を結ぶことよりも、相互の信頼関係を築くための対話が重視されます。
【第2段階】関係と契約の明確化
コンサルティングの目的、範囲、期間、役割分担、費用などを明確にします。
ここでは、形式的な契約書の内容だけでなく、心理的な側面、つまり「お互いに何を期待しているのか」を率直に話し合う「心理的契約」が極めて重要になります。
【第3段階】情報収集と診断
コンサルタントは、会議への参加、メンバーへのインタビュー、アンケートなどを通じて、組織内で何が起こっているのかを観察し、情報を収集します。
ただし、その目的はコンサルタントが一方的に診断を下すことではありません。
集めた情報をクライアントにフィードバックし、クライアント自身が「我々の組織では、このようなことが起こっているのか」と気づき、自ら診断を下すプロセスを支援します。
【第4段階】介入の計画と実行
診断の結果に基づき、具体的な介入活動を計画し、実行します。
介入には、個人のコーチング、チームビルディングのワークショップ、部門間の対話を促進するミーティングのデザインなど、様々な形態があります。
重要なのは、これらの介入がクライアントの主体性を引き出し、学習を促すように設計されていることです。
【第5段階】評価とフィードバック
実行した介入がどのような影響をもたらしたかを評価し、その結果をクライアントと共有します。
計画通りに進んだこと、予期せぬ結果が生まれたことの両方から学び、次のステップへと繋げていきます。
【第6段階】関係の縮小と終結
クライアント組織が自己診断能力と問題解決能力を身につけ、コンサルタントへの依存度が低くなってきたら、徐々に関係を縮小し、最終的には契約を終結させます。
理想的な終結は、クライアントが「もうあなたがいなくても、私たち自身でやっていけます」と自信を持って言える状態になることです。
プロセスコンサルティングが組織にもたらす真の価値

プロセスコンサルティングの導入は、短期的な問題解決だけでなく、組織に長期的かつ持続的な価値をもたらします。
学習する組織への変革
プロセスコンサルティングの最大の価値は、組織内に「学習する文化」を醸成することです。
メンバーは、問題が発生した際に、他責にしたり、見て見ぬふりをしたりするのではなく、それを自分たちの成長の機会と捉え、対話を通じて主体的に解決策を探求するようになります。
この自己修正能力こそが、変化の激しい時代を生き抜くための最も重要な組織能力となります。
心理的安全性の向上とコミュニケーションの活性化
コンサルタントがファシリテーターとして機能し、メンバー間の率直な対話を支援することで、組織内の心理的安全性が高まります。
「こんなことを言ったら、どう思われるだろうか」といった不安が減少し、誰もが安心して本音で意見を交換できるようになります。
これにより、コミュニケーションが活性化し、部門間の壁が低くなり、組織全体の一体感が醸成されます。
当事者意識とエンゲージメントの向上
自分たちで問題を発見し、解決策を考え、実行するという経験は、メンバー一人ひとりの当事者意識を大きく高めます。
「会社の問題」が「自分たちの問題」となり、仕事へのエンゲージメントが向上します。
やらされ感ではなく、自らの意思で組織をより良くしていくという実感は、働くことの喜びと誇りにつながります。
変化への適応能力の獲得
プロセスコンサルティングを通じて、組織は「変化への対処法」を学びます。
未知の問題に直面したときでも、対話を通じて状況を分析し、協力して解決策を見つけ出し、試行錯誤しながら前進していくという、一連のプロセスを遂行する能力が組織に定着します。
これにより、将来のいかなる環境変化にも、しなやかに対応できるレジリエントな組織が形成されます。
プロセスコンサルタントに求められるスキルとマインドセット

プロセスコンサルティングを成功させるためには、コンサルタントに特有の高度なスキルとマインドセットが求められます。
高度な傾聴力と質問力
相手の話の表面的な意味だけでなく、その背後にある感情や価値観、懸念などを深く理解する傾聴力が不可欠です。
また、相手に答えを教えるのではなく、相手自身の内省を促し、新たな視点や気づきを引き出すような、パワフルな質問を投げかける能力が求められます。
グループダイナミクスの理解
集団の中で、人々がどのように相互に影響を与え合い、どのような非公式な力学が働いているのかを敏感に察知し、理解する能力が必要です。
会議での発言の裏にある人間関係や、組織内の目に見えないタブーなどを読み解く力が、効果的な介入の鍵となります。
自己認識と感情のコントロール
コンサルタント自身が、自分の感情や思考の癖、クライアントに対して抱くかもしれない偏見などを、客観的に認識(メタ認知)する能力が重要です。
クライアントの抵抗や批判に直面したときでも、感情的にならず、冷静に自己をコントロールし、建設的な対応を取る必要があります。
謙虚さと忍耐力
「自分は専門家である」という驕りを捨て、クライアントから学ぶという謙虚な姿勢が不可欠です。
また、組織の変革は一朝一夕には実現しません。
目に見える成果がすぐに出なくても、クライアントのペースを尊重し、辛抱強く寄り添い続ける忍耐力が求められます。
組織の真の力を解き放つために

プロセスコンサルティングは、単なる問題解決の手法ではありません。
それは、組織という生命体が、自らの力で健康を維持し、成長していくための自己治癒力を取り戻すプロセスを支援する、人間的なアプローチです。
コンサルタントが輝かしい「スター」になるのではなく、クライアントである組織の人々一人ひとりが、自らの職場で「主役」となることを目指します。
短期的な業績向上や効率化だけを求めるならば、従来型のコンサルティングの方が即効性があるかもしれません。
しかし、変化を乗り越え、持続的に成長し続ける「学習する組織」を本気で目指すならば、プロセスコンサルティングは、他の何にも代えがたい価値を提供してくれるでしょう。
それは、時間と労力を要する、決して平坦ではない道のりです。
しかし、その先には、メンバーが互いに信頼し、主体的に学び合い、誇りを持って働く、真に強い組織の姿が待っているはずです。



