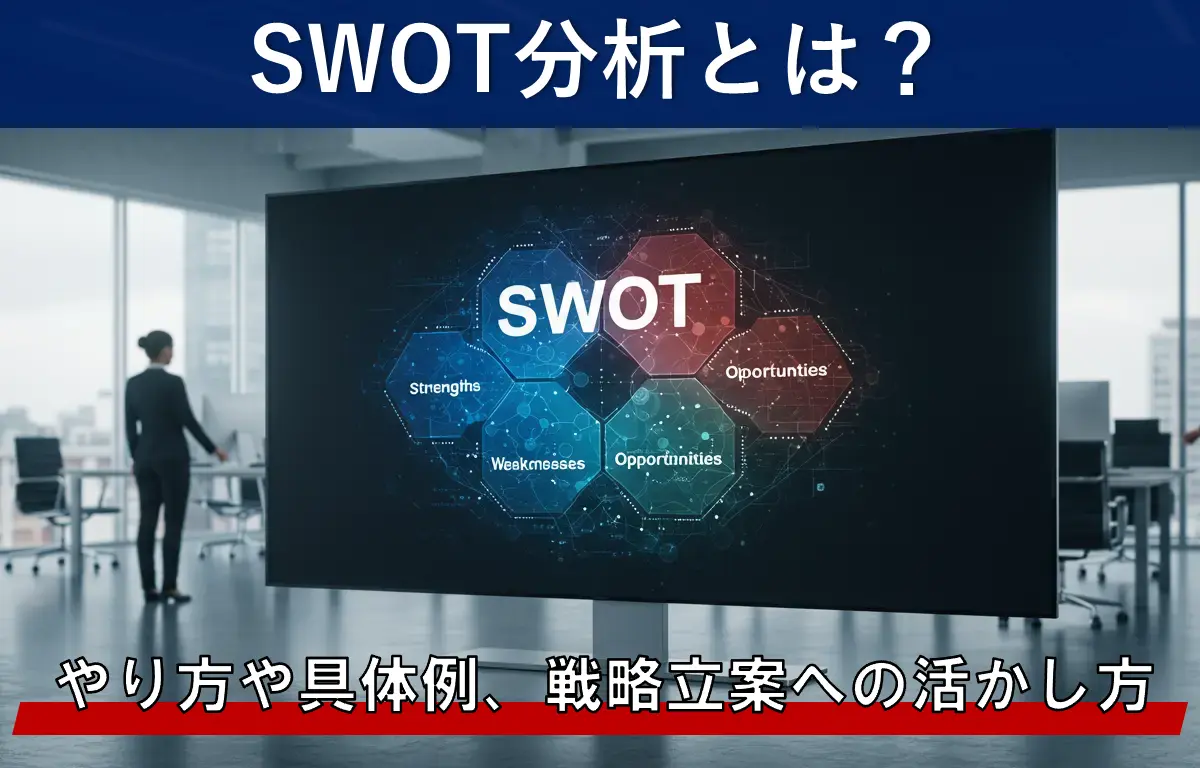
SWOT分析とは?やり方や具体例、戦略立案への活かし方を詳しく紹介
最終更新日:2025/09/09
SWOT分析とは?
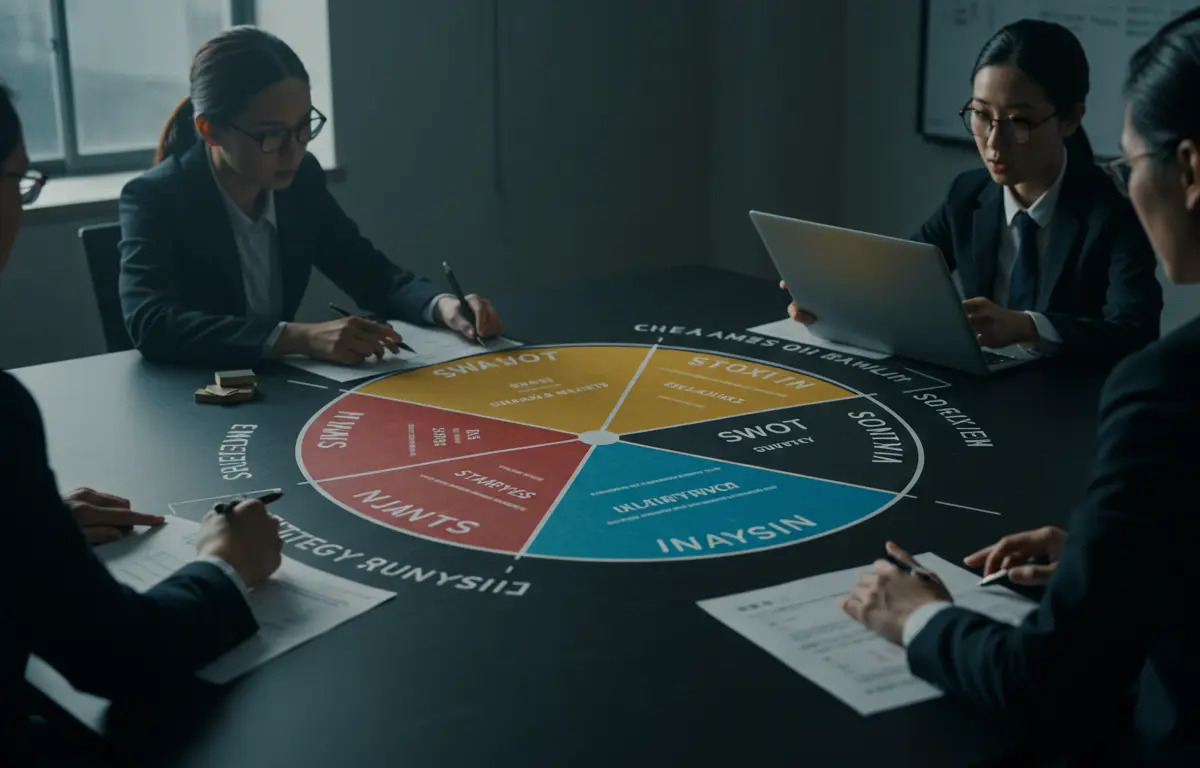
激しく変化し、先行き不透明な現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長し、競争優位性を確立するためには、自社の現状を正確に把握し、進むべき方向を明確に定める戦略的な意思決定が不可欠です。
しかし、「自社の本当の強みは何なのか?」、「市場にはどのようなチャンスが眠っているのか?」、「見過ごしている脅威はないか?」といった問いに、客観的かつ体系的に答えることは容易ではありません。
このような経営の根幹に関わる問いに、明確な指針を与えてくれる強力なフレームワーク、それが「SWOT分析」です。
SWOT分析は、経営戦略や事業計画を策定する際に用いられる、古典的かつ最もポピュラーな分析手法の一つです。
この分析法は、組織や個人を取り巻く環境を「内部環境」と「外部環境」の二つの軸で捉え、さらにそれぞれを「プラス要因」と「マイナス要因」に分類することで、現状を多角的に分析します。
具体的には、以下の4つの要素の頭文字を取って「SWOT」と名付けられています。
・Strength(強み):目標達成に貢献する、自社の内的なプラス要因。
・Weakness(弱み):目標達成の障害となる、自社の内的なマイナス要因。
・Opportunity(機会):目標達成に貢献する、自社の外的なプラス要因。
・Threat(脅威):目標達成の障害となる、自社の外的なマイナス要因。
SWOT分析の最大の特徴は、自社でコントロール可能な「内部環境」と、自社ではコントロールが難しい「外部環境」を分けて分析する点にあります。
これにより、自社の「強み」を活かして市場の「機会」を最大限に捉えるにはどうすればよいか、また、自社の「弱み」を認識し、外部からの「脅威」をいかに回避または克服するか、といった具体的な戦略オプションを導き出すことが可能になります。
そのシンプルさと汎用性の高さから、大企業の経営戦略立案から、中小企業の事業改善、さらには個人のキャリアプランニングに至るまで、幅広い領域で活用されています。
今回は、このSWOT分析の歴史的背景から、具体的な分析手順、実践的な活用法、そして分析をより深化させるための応用テクニックまで、その全貌を紹介していきます。
SWOT分析の歴史と発展

SWOT分析は、今日、世界中のビジネススクールや企業で教えられ、実践されている基本的なフレームワークですが、その起源は1960年代にまで遡ります。
このフレームワークがどのように生まれ、発展してきたかを知ることは、その本質的な価値を理解する上で役立ちます。
SWOT分析の起源として最も有力視されているのは、1960年代から70年代にかけて、スタンフォード大学研究所で実施された一連の研究プロジェクトです。
このプロジェクトは、米国のフォーチュン500に名を連ねる大企業の多くで、なぜ長期的な経営計画が失敗に終わるのか、その原因を解明することを目的としていました。
プロジェクトを率いた経営コンサルタントのアルバート・ハンフリーは、数千社に及ぶ企業へのインタビューと詳細なデータ分析を行いました。
その結果、成功する企業計画には、組織内外の様々な要因を体系的に評価し、それに基づいた現実的な目標設定が行われているという共通点が見出されました。
当初、この分析モデルは「SOFT分析」と呼ばれていました。
・Satisfactory(満足):現状において良い点。
・Opportunity(機会):将来における良い点。
・Fault(欠点):現状における悪い点。
・Threat(脅威):将来における悪い点。
しかし、ハンフリーは後に「Fault(欠点)」をより内的な要因を示す「Weakness(弱み)」に、「Satisfactory(満足)」を「Strength(強み)」に置き換え、現在のSWOTの形が確立されたと言われています。
この研究を通じて開発されたSWOT分析は、複雑な企業の状況を、4つのシンプルな象限に整理し、戦略的な対話のたたき台を提供する画期的なツールとして、ビジネス界に急速に広まっていきました。
その後、ハインツ・ウェイリックをはじめとする多くの経営学者によって、SWOT分析はさらに発展を遂げます。
特にウェイリックが1980年代に提唱した「クロスSWOT分析(TOWSマトリックス)」は、SWOTの4要素をただリストアップするだけでなく、それらを戦略的に組み合わせることで、具体的な行動計画へと繋げる手法として、SWOT分析の実用性を飛躍的に高めました。
このように、SWOT分析は単なる一人の天才の発明ではなく、企業の現実的な課題に対する真摯な探求と、多くの研究者による知的な発展の歴史を経て、今日に至る強力な戦略ツールとして磨き上げられてきたのです。
SWOT分析の4つの要素を深く理解する

SWOT分析を効果的に行うためには、S、W、O、Tの4つの要素がそれぞれ何を意味するのかを、具体的に、かつ深く理解することが不可欠です。
ここでは、各要素を分析する際の視点や具体例を紹介します。
内部環境分析:自社のコントロール可能な要因
内部環境とは、自社の努力や意思決定によってコントロールが可能な、組織内部の要因を指します。
これらは、競合他社と比較した際の、自社の相対的な特徴として捉えることが重要です。
S - Strength(強み)
自社の目標達成に貢献する、組織内部のプラス要因です。
これは、競合他社よりも優れている点や、顧客から高く評価されている独自の資源や能力を指します。
(視点の例)
・特許や独自の技術、ノウハウを持っているか?
・ブランドイメージや顧客からの信頼は高いか?
・優秀な人材や独自の組織文化があるか?
・強固な財務基盤や効率的な生産体制を持っているか?
・顧客との良好な関係性や強力な販売網があるか?
(具体例)
「長年の研究開発で培った独自の画像処理技術」、「若手社員が積極的に挑戦できる企業文化」、「全国を網羅する自社物流ネットワーク」など。
W - Weakness(弱み)
自社の目標達成の障害となる、組織内部のマイナス要因です。
これは、競合他社と比較して劣っている点や、不足している経営資源などを指します。
弱みを客観的に認識することは、時として痛みを伴いますが、改善に向けた第一歩として極めて重要です。
(視点の例)
・競合と比べてブランド認知度が低いか?
・特定の技術や人材が不足していないか?
・製品ラインナップが時代遅れになっていないか?
・非効率な業務プロセスや縦割りの組織構造はないか?
・財務状況に脆弱性はないか?
(具体例)
「主力商品の市場シェアが年々低下している」、「DXに対応できる人材が不足している」、「意思決定プロセスが長く、市場の変化に迅速に対応できない」など。
外部環境分析:自社のコントロールが難しい要因
外部環境とは、自社の努力だけではコントロールすることが難しい、組織を取り巻く外部の要因を指します。
これらは、市場、競合、顧客、社会、技術など、マクロな視点から捉える必要があります。
O - Opportunity(機会)
自社の目標達成にとって追い風となる、外部環境のプラスの変化や潮流です。
これらの機会をいち早く察知し、自社の強みを活かして活用することで、事業を大きく成長させることができます。
(視点の例)
・市場規模が拡大しているか?新たな顧客層は存在するか?
・法改正や規制緩和が自社に有利に働く可能性はあるか?
・新しい技術の登場によって、新商品開発やコスト削減の可能性は生まれているか?
・顧客のライフスタイルや価値観の変化が、自社の商品やサービスへの需要を高めているか?
・競合他社の撤退や経営不振といった状況はあるか?
(具体例)
「健康志向の高まりによるオーガニック食品市場の拡大」、「リモートワークの普及によるクラウドサービスの需要増」、「円安によるインバウンド需要の増加」など。
T - Threat(脅威)
自社の目標達成にとって向かい風となる、外部環境のマイナスの変化や潮流です。
これらの脅威を事前に認識し、対策を講じることで、事業へのダメージを最小限に食い止めることができます。
(視点の例)
・強力な新規参入者や代替品の登場の可能性はあるか?
・市場が縮小傾向にないか?顧客のニーズが変化していないか?
・法規制の強化や、不利な業界標準の策定の動きはないか?
・原材料価格の高騰や、サプライチェーンの寸断リスクはないか?
・景気後退や、人口動態の変化による長期的な影響はないか?
(具体例)
「安価な海外製品の流入による価格競争の激化」、「若者の〇〇離れによる市場縮小」、「個人情報保護規制の強化によるマーケティング活動の制限」など。
SWOT分析の実践ステップ

SWOT分析は、正しい手順を踏むことで、その効果を最大限に発揮します。
ここでは、個人またはチームでSWOT分析を実施するための、具体的な5つのステップを紹介します。
ステップ1:分析の目的とテーマを明確にする
まず最初に、「何のためにSWOT分析を行うのか」という目的を明確にします。
例えば、「会社全体の5年後の経営戦略を考える」、「特定事業の来年度のマーケティング計画を立てる」、「個人のキャリアプランを見直す」など、目的によって分析のスコープ(範囲)や視点が大きく変わります。
目的が曖昧なまま分析を始めると、議論が発散し、有益な結論が得られません。
ステップ2:各要素の情報を洗い出す(ブレインストーミング)
設定したテーマに基づき、S・W・O・Tの4つの要素それぞれについて、思いつく限りの情報を洗い出していきます。
この段階では、質よりも量を重視し、批判や評価はせずに、自由な雰囲気でアイデアを出すことが重要です。
付箋などを使って、一人一人がアイデアを書き出し、それをホワイトボードなどに貼り付けていく手法(ブレインストーミング)が有効です。
・内部環境(S, W)については、社内の各部門のメンバーからヒアリングしたり、顧客満足度調査や従業員意識調査のデータを参考にしたりすると、より客観的な情報を得られます。
・外部環境(O, T)については、業界ニュース、市場調査レポート、政府の統計データ、競合他社の動向などを幅広く収集することが重要です。
PEST分析(政治、経済、社会、技術)などのフレームワークを活用するのも良いでしょう。
ステップ3:洗い出した情報を整理・吟味する
ブレインストーミングで出てきた多数の情報を、整理し、吟味していくステップです。
・重複している意見や、関連性の高い意見をグルーピングします。
・本当に重要な要因は何か、優先順位をつけます。
全ての要因に一度に対応することは不可能です。
目標達成へのインパクトが大きいと思われる要因を、いくつか絞り込むことが重要です。
・事実と意見を区別します。
「〇〇が弱いと思う」という意見だけでなく、「〇〇の市場シェアが過去3年で10%低下している」といった、客観的な事実(データ)に基づいているかを確認します。
ステップ4:クロスSWOT分析で戦略を立案する
ここがSWOT分析の最も重要なステップです。
洗い出した4つの要素を、戦略的に掛け合わせることで、具体的な行動計画へと繋げていきます。
この手法を「クロスSWOT分析」または「TOWSマトリックス」と呼びます。
強み(S)× 機会(O):積極化戦略
自社の「強み」を活かして、市場の「機会」を最大限に活用する戦略です。
最も望ましい戦略であり、事業を大きく成長させる可能性があります。
(例:自社の高い技術力(S)を活かして、成長中の〇〇市場(O)向けの新製品を開発する)
強み(S)× 脅威(T):差別化戦略
自社の「強み」を活かして、外部からの「脅威」を回避または無力化する戦略です。
競合他社との差別化を図る上で重要となります。
(例:高いブランド力(S)を武器に、価格競争の激化(T)の影響を受けにくい高付加価値市場に注力する)
弱み(W)× 機会(O):改善・強化戦略
市場の「機会」を捉えるために、自社の「弱み」を克服または改善する戦略です。
弱みを補うために、他社との提携(M&A)などを検討することもあります。
(例:拡大するEC市場(O)の機会を逃さないために、自社の弱いオンライン販売チャネル(W)を強化する)
弱み(W)× 脅威(T):防衛・撤退戦略
事業へのダメージを最小限に抑えるために、「脅威」の影響を直接受けやすい「弱み」を持つ事業から、撤退または縮小を検討する、最悪の事態を避けるための防衛的な戦略です。
(例:市場縮小(T)が予測される分野で、かつ自社の競争力も低い(W)事業から、段階的に撤退する)
ステップ5:具体的なアクションプランに落とし込む
クロスSWOT分析で導き出された戦略を、具体的な行動計画に落とし込みます。
「何を(What)」、「誰が(Who)」、「いつまでに(When)」、「どのように(How)」実行するのかを明確にし、計画の実行と進捗管理ができる状態にします。
このアクションプランがあって初めて、SWOT分析は「分析のための分析」で終わらず、実践的な成果へと結びつきます。
SWOT分析を成功させるためのコツと注意点

SWOT分析はシンプルであるがゆえに、やり方次第でその質が大きく変わります。
ここでは、分析をより有益なものにするためのコツと、陥りがちな注意点を紹介します。
成功のためのコツ
多様な視点を取り入れる
分析を行う際は、経営層だけでなく、営業、開発、マーケティング、人事など、様々な部門や役職のメンバーが参加することが望ましいです。
多様な視点が加わることで、より網羅的で客観的な分析が可能になります。
客観的なデータや事実を基にする
「なんとなく強みだと思う」といった主観的な意見だけでなく、市場シェアのデータ、顧客アンケートの結果、財務諸表といった客観的な事実に基づいて分析を行うことで、議論の質が高まります。
分析の目的を常に意識する
分析の過程で議論が白熱すると、本来の目的を見失いがちです。
「この分析は、何を決めるために行っているのか?」という原点に、定期的に立ち返ることが重要です。
陥りがちな注意点
S/WとO/Tを混同する
「営業力が高い」のは内部環境である「強み(S)」ですが、「市場が拡大している」のは外部環境である「機会(O)」です。
自社でコントロール可能か否か、という基準で両者を明確に区別する必要があります。
リストアップで満足してしまう
SWOTの4つの要素を洗い出しただけで、分析が終わったと満足してしまうケースが非常に多いです。
最も重要なのは、その後の「クロスSWOT分析」を通じて、具体的な戦略へと昇華させるプロセスです。
完璧を求めすぎない
SWOT分析は、未来を完全に予測するためのツールではありません。
あくまで、現時点での仮説を立て、戦略的な意思決定を行うためのたたき台です。
全ての情報を網羅しようと時間をかけすぎるよりは、重要なポイントに絞って、迅速に次のアクションに繋げることが重要です。
企業の活用事例から学ぶ

SWOT分析が実際の企業でどのように活用され、戦略に結びついているのか、具体的な事例(※あくまで一般的な分析例であり、各社の公式見解ではありません)を通じて見ていきましょう。
事例1:大手コーヒーチェーンA社
・強み(S):高いブランド力、全国に展開する直営店舗網、質の高い接客。
・弱み(W):コンビニコーヒーなど低価格帯との競争、店舗運営コストの高さ。
・機会(O):健康志向の高まり、リモートワークの普及による「第三の場所」としての需要増。
・脅威(T):原材料(コーヒー豆)価格の高騰、異業種からのカフェ事業参入。
・クロスSWOT戦略(一例)
(S×O):高いブランド力と店舗空間を活かし、健康志向のフードメニューを強化。
リモートワーカー向けの快適な電源・Wi-Fi環境を整備する。
(W×T):原材料高騰の影響を吸収するため、高価格帯のスペシャルティコーヒーの比率を高め、低価格帯との競争を避ける。
同時に、モバイルオーダーシステムを導入し、店舗運営の効率化を図る。
事例2:地方の中小製造業B社
・強み(S):特定の分野における高い技術力(職人技)、顧客との長期的な信頼関係。
・弱み(W):経営者の高齢化と後継者不足、営業・マーケティング人材の不足。
・機会(O):海外での日本製品への関心の高まり(インバウンド、越境EC)。
・脅威(T):若者の製造業離れによる人材採用難、大手企業による類似品の開発。
・クロスSWOT戦略(一例)
(S×O):高い技術力をアピールする動画コンテンツを作成し、SNSや越境ECサイトで海外向けに発信する。
(W×O):営業・マーケティングの弱みを補うため、海外展開に強みを持つ専門商社と提携する。
(W×T):後継者問題を解決するため、M&Aによる事業承継を検討し始める。
まとめ:戦略的意思決定の第一歩

SWOT分析は、複雑で混沌としたビジネス環境の中で、自社の立ち位置を冷静に見つめ、進むべき航路を照らし出すための、強力な羅針盤です。
このフレームワークの真価は、内部環境と外部環境、プラス要因とマイナス要因という4つのシンプルな視点を提供することで、思考を整理し、戦略的な対話を促進する点にあります。
ただし、SWOT分析はあくまでスタート地点です。
分析から導き出された戦略が、具体的なアクションプランに落とし込まれ、粘り強く実行されて初めて、それは真の価値を生み出します。
環境は常に変化し続けます。
一度分析して終わりにするのではなく、定期的にSWOT分析を見直し、戦略をアップデートしていくことが、変化の時代を乗り越えるためには不可欠です。
今回紹介した手順とコツを参考に、ぜひあなたの組織やチーム、あるいはあなた自身のキャリアについて、SWOT分析を実践してみてください。
これまで見えていなかった「強み」や「機会」、そして向き合うべき「弱み」や「脅威」が明確になることで、次の一歩を、より確信を持って踏み出せるようになるはずです。



