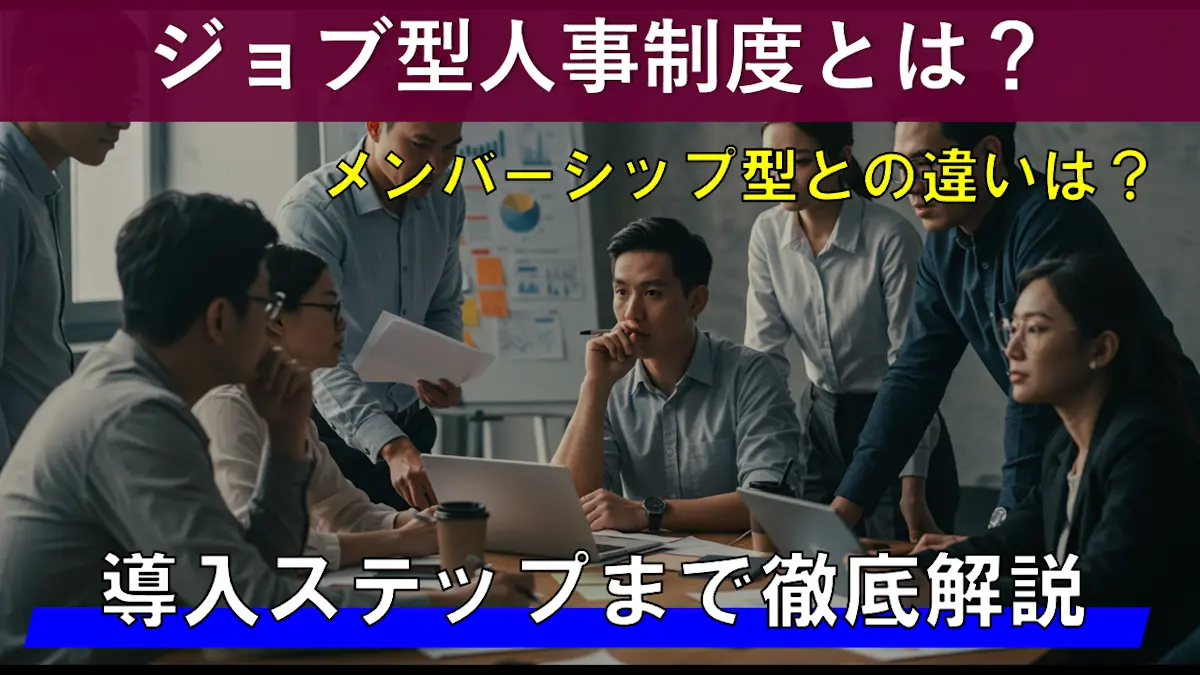
ジョブ型人事制度とは?メンバーシップ型との違いから導入ステップまで紹介
最終更新日:2025/09/07
「がんばっているのに、なぜか給料が上がらない」
「隣の席のベテラン社員、自分より仕事をしていない気がするのに…」
「このまま今の会社にいて、私の専門スキルって本当に身につくのかな?」
会社で働いていると、ふと、こんな『モヤモヤ』を感じたことはありませんか。
その正体は、私たちが長年、当たり前だと思ってきた日本の会社の仕組み、言うなれば「メンバーシップ型」という考え方にあるのかもしれません。
これは、「会社」という名の大きな家族の一員になるようなもの。
新卒で入社し、色々な部署を経験しながら、定年までみんなで一緒に成長していこう、という考え方です。
居心地の良さがある一方で、個人の専門性や成果が、必ずしも評価に直結しにくいという側面も持っていました。
しかし今、その常識が、静かに、けれど確実に変わり始めています。
その変化の主役が、今回お話しする「ジョブ型」という、全く新しい働き方の物差しです。
これはとてもシンプルで、「仕事」というイスがまず先にあり、そのイスに最もふさわしいスキルを持った人が座る、という考え方。
年齢や社歴は関係ありません。
大切なのは、その仕事ができるかどうか、ただそれだけです。
なぜ今、こんな大きな変化が起きているのでしょうか。
この新しい物差しは、私たちの働き方、そして人生を、これからどう変えていくのでしょうか。
今回は、そんな「ジョブ型」という考え方が生まれた歴史を紐解きながら、そのメリットや少し気になる点、そして実際に導入する際に心臓部となる『職務記述書(ジョブディスクリプション)』という設計図まで、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。
ジョブ型人事制度とは

会社と人との関わり方を考えるとき、世の中には大きく二つの考え方があるようです。
一つは、まず会社の中に「仕事」という名のイスを用意する考え方。
もう一つは、まず「人」を会社に迎え入れる考え方です。
ジョブ型人事制度というのは、まさに前者の、イスを先に用意する考え方です。
言うなれば、
「ここには、会社の未来を左右する大切なプロジェクトリーダーのイスがあります」、
「このイスに座るには、人をまとめる力と、英語で交渉できるスキルが必要です」、
「そして、この仕事を見事にやり遂げた方には、これだけの報酬をお約束します」と。
このように、まず仕事の内容、責任、そして必要なスキルをはっきりとさせます。
その上で、そのイスに座るのに最もふさわしい人を、社内や、時には社外から探してきてもらう。
これがジョブ型です。
一方で、これまでの日本の多くの会社は、後者の、まず「人」を迎え入れる考え方でした。
これを「メンバーシップ型」と呼びます。
新卒でたくさんの仲間を一度に会社に迎え入れ、
「君はまず営業を経験してみよう」、
「次は企画部で新しいことを考えてみてほしい」と、色々なイスに座らせながら、時間をかけて会社全体を知る「なんでもできる人」を育てていく。
会社という家族の一員として、長く勤め上げてもらうことが前提の、温かい仕組みでした。
では、なぜ今、イスを先に用意する「ジョブ型」が注目されているのでしょうか。
それは、私たちの働き方や、世の中そのものが大きく変わってきたからです。
例えば、家で仕事をするリモートワークが当たり前になると、誰がどんな仕事をしているのか、少し見えにくくなります。
仕事のイスがあらかじめはっきりしていれば、どこで働いていても、自分の役割が明確になります。
また、世の中の競争は、会社の垣根を越え、世界のプロフェッショナルたちと渡り合う時代になりました。
じっくりと時間をかけて「なんでもできる人」を育てるだけでなく、特定の分野で誰にも負けない「これができる人」の力が必要になってきたのです。
そして何より、「会社にいる時間」ではなく、「どんな仕事をして、どんな成果を出したか」で、正当に評価されたいと願う人が増えてきました。
つまり、「その人は誰か」ということだけでなく、「その人が、どのイスで、何をしてくれるのか」ということに、社会の関心が移ってきたのです。
ジョブ型人事制度は、一人ひとりの専門性を最大限に引き出し、働く人がもっと納得感を持てる社会を作るための、新しい物差しなのかもしれません。
ジョブ型人事制度の起源と歴史的背景

この「ジョブ型」という考え方、そのルーツを探ると、百年以上も昔のアメリカにたどり着きます。
時代は、大きな工場が煙を吐き、たくさんの人々が流れ作業でモノを作っていた頃。
そこでは、誰が何をするのかが曖昧で、仕事の進め方も人それぞれでした。
そんな混沌とした様子を見て、「もっと効率よく、もっと合理的に仕事を進める方法はないだろうか」と考えた、ひとりの経営学者が現れます。
フレデリック・テイラーという人物です。
彼は、ごちゃごちゃになった仕事の山を、まるでパズルを解くように、一つひとつのピースにきれいに分けていきました。
そして、「あなたの仕事は、このネジを、この速さで締めることです」、「あなたの役割は、完成した製品を、この手順で検査することです」と、一人ひとりの仕事の内容を、紙に書き出して明確にしたのです。
これが、今の「職務記述書」、いわゆる、ジョブディスクリプションの原型になったと言われています。
この考え方は、とても合理的で、分かりやすいものでした。
会社にとっては、誰に何を任せればいいかが一目でわかります。
働く人にとっては、自分の仕事の範囲がはっきりしていて、その仕事をこなせば正当に評価されると感じられました。
この分かりやすさが、やがてアメリカからヨーロッパへと広がり、大きな会社を運営するための、いわば「標準装備」のような考え方として根付いていったのです。
さて、その頃の日本ではどうだったのでしょうか。
日本の会社は、少し違った考え方をしていました。
会社はひとつの「家族」や「村」のようなもので、新しく入ってきた若者たちに、色々な仕事を経験させながら、時間をかけて一人前に育てていく。
田植えもすれば、お祭りもする。
みんなで会社という村を支えていく。
そんな「メンバーシップ型」の温かさが、日本の成長を支えてきたのです。
しかし、時代は変わりました。
グローバル化という大きな波がやってきて、世界中のプロフェッショナルたちと、同じ土俵で競い合うことが当たり前になりました。
そんな中で、日本企業も、「この仕事は、この道のプロに任せたい」と考えるようになったのです。
これが、今、日本の多くの会社で「ジョブ型」への関心が高まっている、大きな歴史の流れと言えるでしょう。
なぜ今、ジョブ型が注目されているのか

昨日までの正解が、今日からは通用しなくなる。
そんな、大きな時代の変わり目に、私たちは立っているのかもしれません。
これまで日本の会社を支えてきた「メンバーシップ型」という考え方は、高度経済成長という、みんなで同じ山を登っていく時代には、とても合った仕組みでした。
しかし、その山の登り方そのものが、今、根本から見直されようとしています。
では、なぜ、人を評価する「物差し」が、新しくなろうとしているのでしょうか。
そこには、いくつかの、もう後戻りはできない大きな変化があります。
一つは、私たちの「働く場所」が、会社という建物に限られなくなったことです。
リモートワークが広がり、会社の壁が、物理的に溶け始めました。
そうなると、「誰が、朝から晩まで席に座っていたか」ということよりも、「その人が、どこで、どんな仕事をしてくれたのか」ということが、ずっと大切になります。
「仕事」というイスがはっきりしていれば、たとえ家で働いていても、自分の役割を見失うことはありません。
二つ目は、世界のプロフェッショナルたちと話すとき、私たちは少し違う「言葉」で話していたのかもしれない、という気づきです。
海外のビジネスパーソンは、「あなたの専門分野は何ですか?」、「どんな仕事のイスに座ってきたのですか?」と尋ねます。
一方で、私たちは、「どのくらい、この会社に尽くしてくれますか?」という想いを大切にしてきました。
どちらが良い悪いではありません。
ただ、世界という同じ土俵で力を合わせるためには、共通の言葉、つまり「仕事」という物差しが必要になってきたのです。
三つ目は、会社の「お医者さん」のあり方が変わってきたことです。
昔は、どんな症状も広く浅く診てくれる、町の「かかりつけ医」のような人材が重宝されました。
しかし今、会社が直面する課題は、「デジタル化」や、「グローバル戦略」といった、より複雑で専門的なものになっています。
お腹が痛いとき、「なんでもできます」という人より、「お腹の専門医」に診てもらいたい。
それと同じように、会社も、特定の分野で誰にも負けないプロの力を求めるようになったのです。
そして最後に、働く私たち一人ひとりの心の中にあった、あの「モヤモヤ」です。
「頑張りが、なぜか評価に結びつかない」。
その原因は、「会社にいる時間」という、古い物差しで測られていたからかもしれません。
新しい「ジョブ型」という物差しは、「あなたが、このイスで、どんな価値を生み出してくれたか」を測るものです。
自分が何をして、どれだけの成果を出せば評価されるのかが、誰の目にもはっきりとわかる。
その透明感が、今の時代に求められているのです。
このように、ジョブ型人事制度は、単なる流行り言葉ではありません。
今の時代の働き方や、組織のあり方に、静かに、そしてまっすぐに応えようとする、必然的な変化の流れと言えるのかもしれません。
メンバーシップ型との違いとは

「ジョブ型」という新しい物差しを深く知るためには、私たちが長年慣れ親しんできた、もう一つの物差し、「メンバーシップ型」と並べてみることが一番の近道かもしれません。
この二つは、まるで違う国で生まれた、考え方の違う二人の人間のようです。
どちらが良い、悪いという話ではなく、大切にしているものが、根本的に違うのです。
その違いを、少し覗いてみましょう。
仲間になるとき、会社は何を見ている?
メンバーシップ型の会社が誰かを仲間に迎え入れるとき、それはまるで「お見合い」のようです。
履歴書に書かれた成績も大切ですが、それ以上に、「この人は、うちの家族と上手くやっていけるだろうか」、「これから先、どんな風に成長してくれるだろうか」と、その人の人柄や将来の可能性に、大きな期待を寄せます。
一方で、ジョブ型の会社は、もっとシンプルです。
「経理のイスが一つ空きました。
このイスに座るには、決算を一人で締められるスキルが必要です」。
その仕事ができるかどうか、つまり即戦力であるかどうかが、何よりも大切にされます。
働き始めてから、どんな道を歩むのか
メンバーシップ型の会社では、「まずは営業で、世の中の厳しさを学んできなさい」、「次は企画部で、新しいアイデアを出す仕事だ」と、会社という大きな家の中で、色々な部屋を経験させてくれます。
これは、会社全体のことを理解する「なんでもできる人」を育てるためです。
これに対してジョブ型の会社では、あなたは「パン職人」として雇われたのなら、基本的にはずっとパンを焼き続けます。
もちろん、パン職人として腕を磨き、いつかはパン屋さんの店長になる道はあるかもしれません。
しかし、突然、明日から魚屋さんになってくれ、と言われることは、まずありません。
私の仕事は、どこからどこまで?
メンバーシップ型の働き方は、少し曖昧なところがあります。
自分の仕事が終わっても、隣の人が困っていたら手伝うのが当たり前。
時には、部署の垣根を越えて、みんなでお祭りの準備をするような、そんな一体感があります。
仕事の範囲が、はっきりと決まっていないのです。
一方、ジョブ型は、とても明確です。
「あなたの仕事は、このパンを、このレシピ通りに、一日百個焼くことです」。
最初に交わした契約書、つまり「職務記述書」に書かれていることが、あなたの仕事の全てです。
それ以上のことを求められることはありませんが、同時に、そこに書かれている責任は、きっちりと果たさなければなりません。
頑張りは、どうやって評価されるの?
メンバーシップ型では、評価はまるで学校の「通知表」のようです。
仕事の成績はもちろんですが、「周りと協力できているか」、「仕事に真面目に取り組んでいるか」といった、日々の頑張りや態度も、大切な評価のポイントになります。
これに対してジョブ型は、「成果報告書」と言えるでしょう。
「パンを、百個焼くという約束でしたね。
あなたは、百二十個焼いてくれました。
素晴らしい成果です」。
どれだけ頑張ったか、というプロセスよりも、どんな結果を出したか、ということが、ストレートに評価に繋がります。
これから先、どんな自分になれるのか
メンバーシップ型の会社では、会社が用意してくれた登山道を、色々な景色を楽しみながら登っていくキャリアが一般的です。
山の頂上に着く頃には、どんな道でも歩ける、経験豊かな登山家になっているかもしれません。
一方、ジョブ型では、「私は、この岩壁を登るプロになる」と、自分で道を選び、その道をひたすら極めていくキャリアが中心になります。
登れる山は一つかもしれませんが、その道の第一人者になれる可能性があります。
このように、二つの考え方は、どちらが優れているというわけではありません。
メンバーシップ型は、みんなで助け合う温かさがある一方で、個人の専門性が評価されにくいという声がありました。
ジョブ型は、自分のスキルで勝負できる分かりやすさがある一方で、自分の仕事が終わればそれで終わり、という少しドライな側面も持っています。
大切なのは、これからの時代、私たちの会社が、そして私たち自身が、どんな働き方を心地よいと感じ、どんな未来を目指していくのか。
その目的に合わせて、二つの物差しを、賢く使い分けていくことなのかもしれません。
世界のビジネス現場では、どう運用されているのか

「ジョブ型」という人事制度は、国や文化が違えば、その色合いも少しずつ異なります。
それぞれの国が歩んできた歴史や、ビジネスに対する価値観が、制度の運用に反映されているからです。
ここでは、主要な国々の事例を覗きながら、その成果と、現実に直面している課題について見ていきましょう。
アメリカ、プロフェッショナルの世界
ジョブ型人事制度のいわば「本場」とも言えるのが、アメリカです。
ここでは、企業と個人は、常に「職務」という明確な契約で結ばれています。
採用時には、企業がまず「職務記述書」、つまり仕事の設計図を提示します。
働く側は、その設計図を見て、「私のスキルと経験なら、この仕事を完璧にこなせます」と、自らを売り込むのです。
この仕組みがもたらす最大の成果は、その「透明性」と「合理性」です。
仕事の範囲や責任がはっきりしているため、採用後のミスマッチが起こりにくい。
そして、その仕事で成果を出せば、年齢や社歴に関係なく、正当な報酬が得られる。
プロフェッショナルが、自らの市場価値を試すには、非常にフェアな環境と言えます。
一方で、この合理性は、時として組織の「体温」を下げることがあります。
個人の成果が最優先されるあまり、部署間の連携や、後進を育てる OJT といった、チーム全体の力が少し弱まる傾向が見られます。
自分の仕事が終われば、それで終わり。
そんな、少しドライな空気が生まれることもあるようです。
ドイツやフランス、秩序と公平性の世界
次に、ドイツやフランスに目を向けてみましょう。
これらの国々では、ジョブ型は、個人の成果を最大化するためというより、むしろ、組織全体の「秩序」と「公平性」を保つための基盤として機能しています。
特に、歴史の長い製造業などでは、「この職務の仕事には、この等級の賃金を支払う」というルールが、労働組合との間で厳格に定められています。
職務記述書は、個人の能力を測るものというより、労使間の公正な契約を担保するための、いわば「公的な文書」としての役割が強いのです。
この仕組みがもたらす成果は、労使関係の「安定性」です。
働く側は、自分の職務と待遇が明確に守られているという安心感の中で、仕事に集中できます。
企業側も、人件費の管理がしやすく、合理的な人員配置が可能になります。
一方で、この厳格さは、変化への「柔軟性」という点では課題を抱えることがあります。
決められた職務以外の業務を、臨機応応変に依頼することが難しい。
新しいビジネスが生まれ、これまでになかった仕事が発生した際に、その職務を定義し、賃金テーブルに位置づけるまでに、少し時間がかかってしまうこともあるようです。
そして、日本。移行期の葛藤と、可能性
さて、私たちの日本は、今、まさにこの大きな変化の渦中にいます。
長年慣れ親しんだ「メンバーシップ型」の良さを残しつつ、「ジョブ型」の合理性を取り入れようと、多くの企業が試行錯誤を繰り返しています。
いわゆる、「ハイブリッド運用」です。
なぜ、日本が今、この変化を必要としているのか。
それは、グローバルという同じ土俵で戦うための、専門性の高い人材が必要だから。
リモートワークという、新しい働き方が定着したから。
そして何より、「会社にいる時間」ではなく、「どんな価値を生んだか」で評価されたい、という働く人の声に応えるためです。
しかし、この移行には、特有の難しさが伴います。
まず、社内に存在する、すべての仕事の価値を定義し、評価する仕組みをゼロから作るには、膨大な時間と労力がかかります。
また、
「みんなで助け合う」という、これまでの文化と、「自分の仕事はここまで」という、新しい考え方の間で、現場に戸惑いが生まれることも少なくありません。
そして、「なんでもできる人」を育ててきた育成方針と、「この道のプロ」を求めるジョ-ブ型との間で、どう整合性を取っていくのかという、根源的な問いにも向き合う必要があります。
大切なのは、他国の制度を、そのまま「輸入」するのではない、ということです。
それは、まるで既製品のスーツを、そのまま着るようなもの。
どこか窮屈で、自分らしさを失ってしまうかもしれません。
そうではなく、アメリカの合理性、ヨーロッパの公平性を参考にしながらも、日本の組織が大切にしてきた「人の繋がり」や「長期的な視点」という強みを活かし、自社の体型にぴったりと合ったスーツを、自分たちで「仕立て直す」。
そんな、賢明で、創造的なアプローチこそが、これからの日本企業には求められているのではないでしょうか。
ジョブ型人事制度の光と影

どんな物事にも、光が当たれば、その反対側には必ず影ができます。
新しい「ジョブ型」という物差しも、私たちの働き方を明るく照らしてくれるたくさんの光がある一方で、気をつけなければならない影の部分も、確かに存在します。
ここでは、その光と影、両方をじっくりと見ていくことにしましょう。
ジョブ型の「光」の部分
まず、この新しい物差しが、私たちの職場にどんな光をもたらしてくれるのでしょうか。
一つ目の光は、「透明感」です。
自分の仕事の内容、責任の範囲、そして何をどこまでやれば評価されるのかが、まるでガラス張りのように、誰の目にもはっきりとわかるようになります。
これは、働く人にとって、「自分は今、何を期待されているのか」という地図を手にしているようなもの。
ゴールがはっきり見えるからこそ、安心して、まっすぐに自分の仕事に打ち込めるのです。
二つ目の光は、「専門性」という輝きです。
「この仕事なら、あの人に任せたい」。
会社は、その道のプロフェッショナルが持つ特別なスキルに、正当な対価を払って力を借りることができます。
働く人にとっても、自分の腕一本で勝負できる場所があるというのは、大きなやりがいと誇りに繋がります。
年齢や社歴に関係なく、自分の専門性が輝く場所を見つけやすくなるのです。
三つ目の光は、「納得感」のある評価です。
「頑張ったことが、まっすぐに評価される」。
仕事のイスごとに、期待される成果があらかじめ決まっているので、評価の基準がとてもシンプルになります。
これまでのような、「上司との相性」や、「声の大きさ」といった、少し曖昧な要素が入り込む余地が少なくなり、多くの人が納得感を持って、自分の評価を受け入れやすくなるでしょう。
ジョブ型の「影」の部分
一方で、この物差しが落とす影の部分にも、私たちは目を向けなければなりません。
一つ目の影は、「柔軟性」が失われるかもしれない、ということです。
「あなたの仕事は、この畑を耕すことです」と決められていると、隣の畑が少し大変そうでも、なかなか手伝いに行きにくい空気が生まれるかもしれません。
会社全体で何か大きな問題が起きた時に、「それは私の仕事ではありませんから」という言葉が、聞かれるようになる。
そんな少し寂しい職場になってしまう可能性を、この制度は秘めています。
二つ目の影は、導入するまでの「途方もない道のり」です。
会社にある、すべての仕事のイスに、一つひとつ名前をつけて、「このイスの仕事内容はこうです」、「責任の重さはこれくらいです」と、説明書を作っていく作業。
これは、会社中の仕事の、いわば大掃除と棚卸しをするようなもので、想像を絶する時間とエネルギーが必要になります。
三つ目の影は、「一体感」という温かさが、少し冷めてしまうかもしれない、ということです。
一人ひとりが自分の仕事のプロフェッショナルになることは、素晴らしいことです。
しかし、それは時として、個人競技の集まりのようになってしまう危険性もはらんでいます。
みんなで助け合い、汗を流し、一つの目標に向かっていく。
そんな、これまでの日本の会社が大切にしてきた「家族」のような温かさが、少しずつ失われていくかもしれません。
四つ目の影は、「成長の機会」が、狭まってしまうかもしれない、ということです。
「未経験者お断り」。
仕事のイスがあらかじめ決まっているということは、そのイスに座るためのスキルを持っていない人は、なかなか仲間に入ることが難しくなる、ということです。
新卒で入った若者が、色々な仕事を経験しながら、ゆっくりと成長していく。
そんな、日本の会社が持っていた「人を育てる」という大切な文化が、少しずつ形を変えていく可能性があります。
このように、ジョブ型は、たくさんの魅力的な光を放つ一方で、私たちがこれまで大切にしてきた何かを、影の中に置いてきてしまうかもしれない。
そんな側面も持っています。
大切なのは、「何のために、この新しい物差しを使うのか」という目的を、決して見失わないこと。
それこそが、この大きな変化を乗り越えるための、最初の、そして最も重要な一歩と言えるでしょう。
導入のステップと、成功へ向けた勘所

ジョブ型人事制度の導入は、単に海外の制度を輸入するような単純な作業ではありません。
それは、自社の経営戦略、組織の文化、そして働く人々一人ひとりの意識にまで踏み込む、極めて繊細で、そして大掛かりな「組織改革プロジェクト」です。
その成功は、いかに周到な設計と、丁寧なコミュニケーションを行えるかにかかっています。
ここでは、その改革を成功に導くための、主要な4つのステップと、その勘所をご紹介します。
ステップ1、導入目的の明確化。全ての判断の「羅針盤」を持つ
まず、全ての議論の出発点として、「私たちは、なぜ、ジョブ型人事制度を導入するのか」という、その目的を徹底的に明確にする必要があります。
人事制度は、経営戦略を実現するための重要なツールです。
この目的が曖-昧なままでは、プロジェクトは必ず途中で迷走します。
例えば、「グローバル市場で戦える、専門性の高い人材を獲得・育成するため」、「成果を出した人が、年齢に関係なく正当に報われる、透明性の高い組織を作るため」といった、具体的な経営課題と結びつけることが不可欠です。
この最初に掲げた目的こそが、今後、制度設計の細部で判断に迷った時に立ち返るべき、唯一の「羅針盤」となります。
ステップ2、ジョブディスクリプションの整備。制度の「設計図」を描く
ジョブ型人事制度の根幹をなし、その成否を左右するのが、「ジョブディスクリプション」、いわゆる職務記述書です。
これは、制度全体の品質を決める、いわば「設計図」に他なりません。
会社に存在する、一つひとつの職務、つまり「仕事のイス」について、「どのような業務を」、「どのような責任範囲で遂行するのか」、「そのために、どのようなスキルや経験が必要か」を、具体的かつ客観的な言葉で明文化していきます。
この設計図を描く上での勘所は、人事部だけで完結させないことです。
実際にその仕事をしている現場の従業員や、管理職を巻き込み、業務の実態に即した、血の通った内容にすることが極めて重要です。
この設計図の精度が、後の採用、評価、育成といった全てのプロセスの土台となります。
ステップ3、評価・報酬制度との連動。制度を動かす「エンジン」を設計する
ジョブ型は、成果や貢献度に基づいて評価し、報いることが基本思想です。
立派な設計図を描いても、それを動かす「エンジン」、つまり評価と報酬の仕組みが旧式のままでは、制度は機能しません。
「その仕事のイスの価値は、会社全体の中でどれくらいか」
「そのイスで、どのような成果を出せば、どう評価され、報酬に反映されるのか」
これまでのような、勤続年数や年齢といった要素ではなく、仕事の価値と成果に基づいた、新しい評価と報酬のルールを再設計する必要があります。
このエンジンが力強く回って初めて、従業員のモチベーションは向上し、組織の生産性は高まります。
ステップ4、社内への浸透と意識改革。「変化への橋」を架ける
新しい制度は、時に組織に軋轢や不安を生みます。
特に、長年メンバーシップ型に慣れ親しんできた従業員や管理職にとって、ジョブ型への移行は、働き方そのものを変える大きな変化です。
この変化を、単なる「上からの押し付け」で終わらせないために、丁寧なコミュニケーションを通じて、組織全体に「変化への橋」を架ける必要があります。
管理職には、新しい制度の下で、部下をどう評価し、どう育成していくのかを学ぶ研修が不可欠です。
従業員には、なぜ会社が変わろうとしているのか、その背景と目的を、何度も、そして誠実に伝える説明会が欠かせません。
「与えられた仕事をこなす」という意識から、「自分の責任領域で、主体的に成果を出す」という意識へ。
このマインドセットの変革を、組織全体で支援していくことが求められます。
最後に、多くの成功企業が実践している、二つの重要なヒントがあります。
一つは、いきなり全社で一斉に導入するのではなく、まずは特定の部署で試験的に導入してみること。
小さな成功と、そこから得られた学びを次に活かす、段階的なアプローチが、結果として定着への近道となります。
そして、もう一つは、現場との対話を、何よりも大切にすることです。
制度設計のプロセスそのものを、現場の従業員を巻き込んだ「共創プロジェクト」にすること。
その対話の積み重ねこそが、新しい制度を、真に組織の力に変えていくのです。
ジョブディスクリプション、制度の「心臓部」
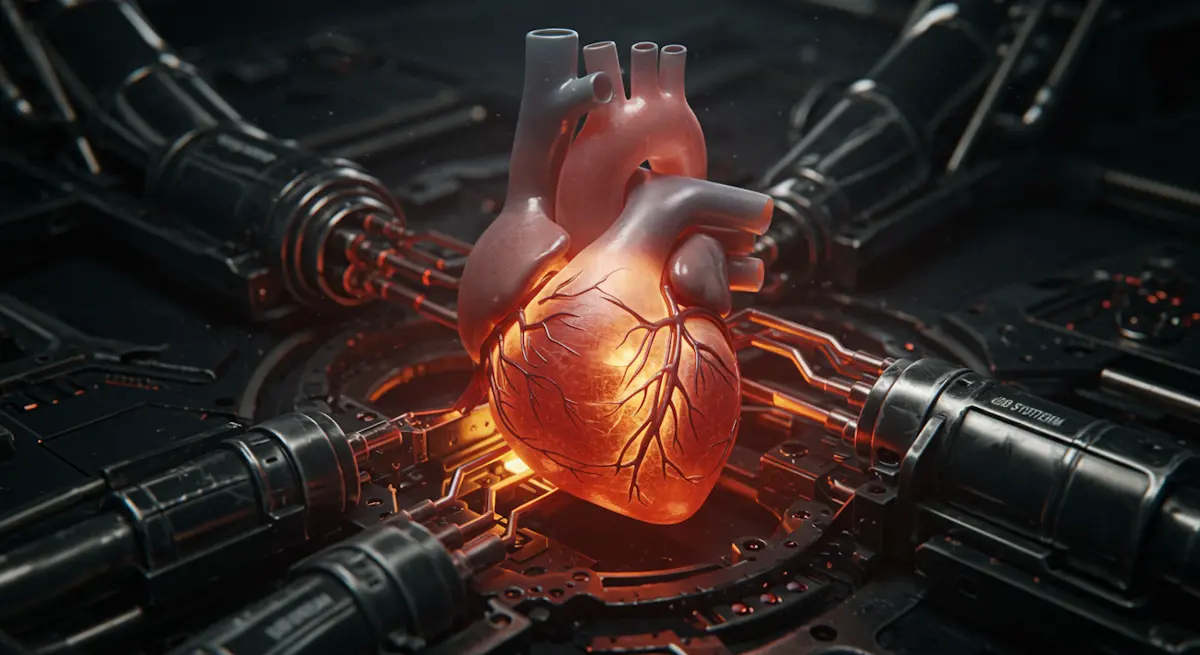
ジョブ型人事制度という、大きな船の心臓部。
それが、ジョブディスクリプションです。
日本語では「職務記述書」と呼ばれます。
これは、会社に存在する一つひとつの「仕事のイス」について、その役割と責任を、具体的かつ明確な言葉で描き出した、いわば制度全体の「設計図」に他なりません。
採用も、評価も、そして報酬も、すべてはこの一枚の設計図を起点として、論理的に組み立てられていきます。
設計図には、何が描かれているのか
では、この重要な設計図には、具体的にどのような情報が記されているのでしょうか。
それは、単なる「仕事内容のリスト」ではありません。
「この仕事は、会社のどの歯車を動かすために存在するのか」、という職務の目的。
「どのような業務を、どこまでの責任範囲で担うのか」、という具体的な役割。
「その役割を果たすには、どのようなスキルや経験が必要か」、という求められる能力。
「どのような成果を測るのか」、という客観的なゴール。
「誰に報告し、誰を導くのか」、という組織の中での立ち位置。
このように、ジョブディスクリプションは、その仕事の存在意義そのものを定義する、極めて戦略的な文書なのです。
なぜ、この設計図が不可欠なのか
この一枚の設計図が、なぜ、これほどまでに重要視されるのでしょうか。
それは、組織が抱える、根深い課題を解決する力を持っているからです。
一つは、採用における「すれ違い」をなくすためです。
これまでの採用は、どこか「お見合い」のような、曖昧な期待感の中で行われることもありました。
しかし、この設計図があれば、会社側も、働く側も、「どんな仕事で、何が求められているのか」を、お互いに誤解なく理解した上で、プロフェッショナルな契約を結ぶことができます。
二つ目は、評価における「モヤモヤ」を解消するためです。
「なぜ、あの人が自分より評価が高いのだろう」。
その不満の多くは、評価の「物差し」が、人によって違って見えることに起因します。
ジョブディスクリプションは、その物差しを、誰の目にも見える形で提示します。
上司のさじ加減といった主観的な要素が入り込む余地を減らし、評価に対する透明性と納得感を、飛躍的に高めるのです。
三つ目は、働く人一人ひとりの「成長の道しるべ」となるためです。
自分が今座っているイスで、どんなスキルが求められ、何が足りないのかが明確になります。
そして、次に目指したいイスに座るためには、どんなスキルを身につければいいのか。
会社にとっても、働く人にとっても、キャリアという旅路の、確かな地図となります。
そして最後に、組織全体の「一貫性」を生み出すためです。
この設計図が全ての土台となることで、等級や、評価や、報酬や、教育といった、人事に関する様々な仕組みが、まるで背骨が通ったように、一つの論理で繋がり、整合性の取れた、強い組織を創り上げることができるのです。
設計図を描く上での、勘所
この重要な設計図を描く上で、いくつか心に留めておくべきことがあります。
まず、決して、机上の空論であってはならない、ということです。
実際にその仕事をしている現場の人々と、何度も対話を重ね、血の通った、リアルな内容にすること。
現場の実態と乖離した設計図は、絵に描いた餅に終わります。
次に、一度描いたら終わり、ではないということです。
ビジネスの状況は、日々刻々と変化します。
それに合わせて、仕事の役割も変わっていくのは当然のこと。
この設計図を、常に最新の状態に保ち続ける、地道な努力が欠かせません。
そして、誰が読んでも、同じように理解できる、シンプルで具体的な言葉で描くこと。
これは、会社と働く人との、大切な「約束の書」です。
その言葉が曖昧であれば、約束そのものが揺らいでしまいます。
ジョブディスクリプションは、制度導入時に一度だけ作る、儀式的な書類ではありません。
それは、会社の成長と共に生き、進化し続ける、人事の「羅針盤」です。
この羅針盤の精度こそが、ジョブ型人事制度という船が、目的地にたどり着けるかどうかを左右する、最大の鍵と言えるでしょう。
評価と報酬、制度を動かす「エンジン」
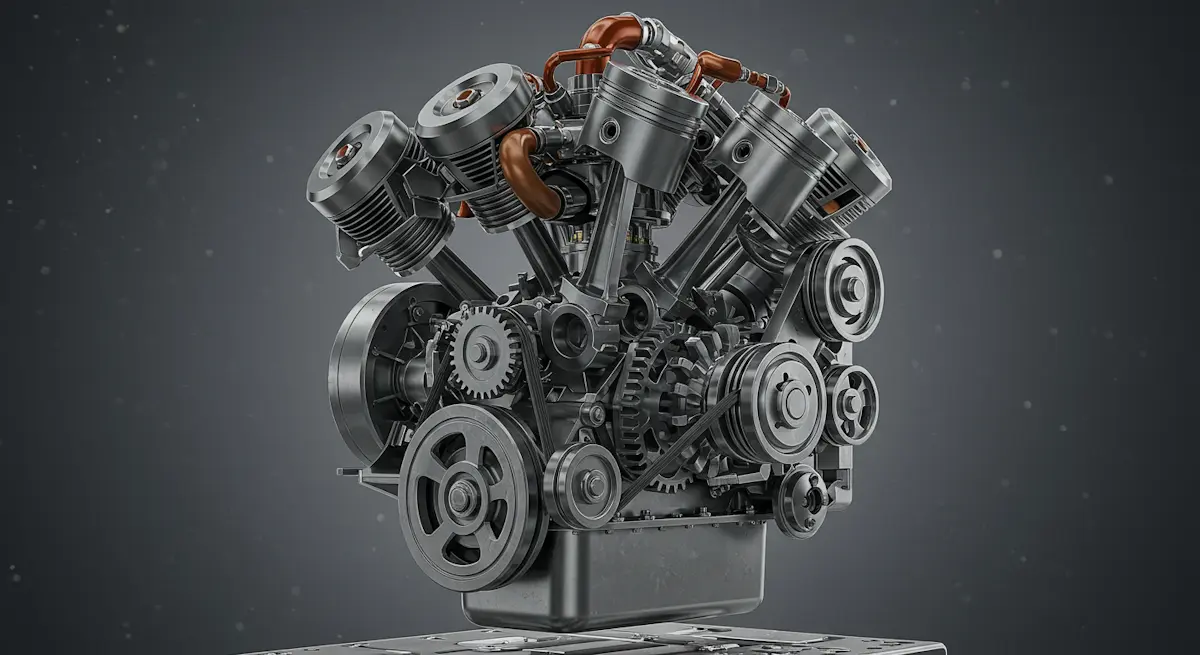
ジョブ型人事制度という、新しい家の「設計図」を描いただけでは、まだ家は完成しません。
その家で、人々が生き生きと暮らし、活動するためには、電気や水道といった、生活を支えるインフラが必要です。
人事制度におけるインフラ、それは「評価」と「報酬」の仕組みです。
この二つが、制度全体を動かす、いわば「エンジン」の役割を果たします。
どんなに立派な設計図を描いても、このエンジンが旧式のままでは、新しい家は機能しないのです。
評価の「物差し」を、根本から変える
まず、評価の考え方そのものを、新しい物差しに持ち替える必要があります。
これまでのメンバーシップ型では、
「その人は、どんな人か」という、人物そのものを総合的に評価する側面が強くありました。
勤務態度や、協調性、将来への期待値といった要素も、大切な評価のポイントでした。
しかし、ジョブ型における評価の主役は、あくまで「仕事のイス」です。
評価の物差しは、とてもシンプルになります。
「そのイスで、何を成し遂げたのか」、という成果。
そして、
「そのイスに座るために求められる能力を、どれだけ発揮できたか」、という専門性。
この二つに、評価の焦点が絞られます。
ここで重要なのは、会社にいる全ての人を、同じ物差しで測るのではない、ということです。
営業のイスと、開発のイスでは、求められる成果も、必要な能力も、当然異なります。
だからこそ、一つひとつのジョブディスクリプションに連動した、個別の評価基準を設計することが、不可欠となるのです。
報酬の「哲学」を、再定義する
評価の物差しが変われば、当然、報酬、つまりお給料の考え方も変わります。
ジョブ型の報酬における、最も大切な哲学。
それは、「同一職務、同一報酬」という原則です。
これは、「人に値段をつける」のではなく、「仕事のイスに値段をつける」という、根本的な発想の転換を意味します。
同じ内容、同じ責任範囲の仕事であれば、そこに座っているのが新人であろうと、ベテランであろうと、基本的には同じ水準の報酬が支払われる。
この原則によって、年齢や勤続年数といった、仕事の成果とは直接関係のない要素が、給与に影響しにくくなります。
その結果、誰の目にも公平で、透明性の高い報酬体系が実現できるのです。
制度を機能させるための、実務的な勘所
この新しいエンジンを、スムーズに動かすためには、いくつかの実務的な仕掛けが必要です。
まず、目標設定の仕組みを、仕事のイスごとに見直すこと。
目標管理制度、いわゆる MBO などを、個人の成長目標だけでなく、職務の成果目標としっかりと連動させる必要があります。
次に、評価者の「目線」を揃えること。
評価者である管理職によって、評価の甘辛にばらつきが出てしまっては、制度の公平性が揺らぎます。
そのための、評価者訓練は欠かせません。
そして、評価と報酬が、きちんと連動する給与テーブルを設計すること。
仕事のイスの価値に応じて、給与の幅、つまり給与レンジを明確にすることが、従業員の納得感を高めます。
最後に、評価の結果を、きちんと本人に「対話」を通じて伝えること。
一方的な通知ではなく、何が評価され、次に何を期待されているのかを丁寧にフィードバックする機会が、本人の成長と、制度への信頼を育むのです。
日本企業が向き合うべき、移行期の現実
とはいえ、長年「年功」という考え方に慣れ親しんできた日本の会社で、この新しい哲学をいきなり導入するには、丁寧な配慮が必要です。
昨日まで年功で給与が決まっていたのに、今日から突然、仕事の価値だけで決まる、となれば、組織に大きな混乱や不安が生まれるのは当然です。
そのため、多くの日本企業では、完全なジョブ型に移行するのではなく、「仕事のイスの価値」を基本としながらも、「その人が持つ専門性の高さ」や、「会社全体への貢献度」といった要素も加味する、「複合的な評価制度」を採用するケースが増えています。
ジョブ型という改革が成功するかどうかは、「仕事の定義」と、「評価・報酬の仕組み」という二つの歯車が、きちんと噛み合って回るかにかかっています。
その制度設計の精度と、従業員の納得感こそが、組織全体のパフォーマンスを引き上げる、最も重要な鍵となるのです。
これからのキャリアは、誰が設計するのか

ジョブ型という、新しい物差しが私たちの職場に入ってくるとき。
それは、単に評価や給与のルールが変わる、というだけではありません。
私たち一人ひとりの、「働き手としての生き方」、つまりキャリアに対する考え方そのものを、根本から揺さぶる、大きな変化の始まりなのです。
これまで、私たちのキャリアは、多くの場合、会社が敷いてくれた一本のレールの上を走る旅のようなものでした。
しかし、これからは、そのレールの主導権が、少しずつ、私たち自身の手の中に移ってきます。
「なんでも屋」から、「看板を掲げる専門店」へ
これまでの日本の会社では、「まずは営業で3年」、「次は企画で5年」と、様々な部署を経験し、会社全体のことを幅広く知る、「なんでも屋」のようなゼネラリストが重宝されてきました。
それが、会社が用意してくれた、一つのキャリアの形でした。
しかし、ジョブ型という物差しが主流になると、その価値観は大きく変わります。
評価の軸は、「どれだけ広く知っているか」ということよりも、「この分野で、どれだけ深く、鋭い専門性を持っているか」という点に移っていきます。
それは、まるで商店街のようです。
なんでも揃う便利なスーパーマーケットも大切ですが、「パンなら、あの店」、「魚なら、この店」と、自分の名前で看板を掲げる専門店が、その専門性で評価される。
そんな時代が、会社の中にもやってくるのです。
経歴書の「一行目」が変わる
これまで、私たちのキャリアの価値は、「どの会社に、何年勤めているか」ということが、大きな意味を持っていました。
経歴書の一行目に書かれた、会社の名前が、その人の信用を保証してくれたのです。
しかし、これからは、その一行目よりも、その下に続く、「どんな仕事のイスに座り」、「どんな成果を上げてきたのか」という、具体的な職務のリストが、より重い意味を持つようになります。
自分の価値は、会社の看板ではなく、自分自身の「仕事の積み重ね」によって決まる。
その意識が、社内での評価だけでなく、社外の労働市場における、自分の市場価値を考えるきっかけにもなるのです。
会社が渡すのは、「地図」。どの道を行くかは、自分次第
ジョブ型の世界では、会社はもう、あなたが行くべき場所まで続く、一本のレールを敷いてはくれないかもしれません。
その代わりに、会社は、「この会社という国には、こんな街や、あんな山がありますよ」、「そして、それぞれの場所に行くには、こんなスキルという名の装備が必要ですよ」という、一枚の精巧な「地図」を渡してくれます。
どの街を目指すのか。
どの山に登るのか。
そのために、どんな装備を、どうやって手に入れるのか。
そのルートを設計し、旅の計画を立てるのは、他の誰でもない、あなた自身です。
もちろん、会社もその旅を支援してくれます。
定期的にキャリアについて話し合う面談の機会を設けたり、新しい装備を手に入れるための研修制度を整えたり。
しかし、その機会をどう活かすかは、個人の主体性に委ねられます。
「プロフェッショナル」として生きる、ということ
仕事のイスが明確になるということは、会社という垣根を越えて、自分のスキルを試すチャンスが増える、ということでもあります。
転職や、副業といった選択肢も、より身近なものになるでしょう。
自分のジョブディスクリプション、つまり仕事の設計図が、そのまま社外への「名刺」代わりになるからです。
ジョブ型という変化の波は、私たち働く一人ひとりに対して、「あなたは何ができますか?」、「どんな価値を提供できますか?」と、静かに、しかし、まっすぐに問いかけてきます。
それは、会社という組織の一員であると同時に、自分の名前で仕事をする、一人の「プロフェッショナル」としての生き方が求められる時代の、幕開けなのかもしれません。
これからの日本企業が、向き合うべき課題

ジョブ型人事制度は、世界のビジネスシーンにおける、いわば「標準語」です。
しかし、その標準語を、長年独自の「方言」で対話してきた日本の会社が、そのまま使うのは、簡単なことではありません。
単純に制度を「輸入」するだけでは、組織のあちこちで、言葉が通じない、という事態が起こり得ます。
日本企業には、日本企業ならではの、賢明な適応が求められるのです。
日本企業が乗り越えるべき、三つの壁
なぜ、この新しい標準語は、日本の組織にすんなりと馴染まないのでしょうか。
そこには、私たちが長年かけて築き上げてきた、根深い三つの壁が存在します。
一つ目の壁は、「組織文化」です。
年功序列や、終身雇用という考え方は、単なる制度ではなく、戦後の日本経済を支えてきた、一種の「成功体験」であり、価値観です。
「仕事」というドライな契約で人を割り当てる、という考え方に、どこか寂しさや違和感を覚える人がいるのは、自然なことかもしれません。
二つ目の壁は、「仕事の曖昧さ」です。
これまでの日本の職場では、
「それは私の仕事ではありません」という言葉は、歓迎されませんでした。
自分の仕事が終われば、周りを手伝う。
そんな、境界線のない柔軟性が、チームの強みだと信じられてきたからです。
そのため、そもそも「仕事を言語化する」という文化が、あまり育ってこなかったのです。
三つ目の壁は、「人材育成の哲学」です。
様々な部署を経験させ、会社全体のことを理解するゼネラリストを、時間をかけて育てる。
これが、日本の会社が大切にしてきた、人材育成の王道でした。
特定の仕事に人を固定するジョブ型は、この哲学と、真っ向から対立する側面を持っています。
可能性は、「第三の道」にある
こうした高い壁がある一方で、この変化の波を、自社の強さに変えようと挑戦する企業が増えているのも、また事実です。
その多くが選んでいるのは、どちらか一方を完璧に真似するのではなく、二つの制度の良いところを組み合わせる、「ハイブリッド型」という、いわば「第三の道」です。
例えば、グローバルな競争に直面している、エンジニアや、企画部門といった、専門性が勝負を分ける部署に限定して、ジョブ型を導入する。
あるいは、評価や報酬の仕組みだけを、「仕事の価値」を基準とするジョブ型に近づけ、評価の透明性と納得感を高める。
このように、自社の文化や、戦略的な優先順位に合わせて、段階的に、そして柔軟に新しい物差しを取り入れていく。
それこそが、日本企業にとって、最も現実的で、賢明なアプローチと言えるでしょう。
鍵を握るのは、「会社と個人の、新しい関係」
ジョブ型人事制度という変革の本質は、単なる仕組みの入れ替えではありません。
それは、会社と、働く人一人ひとりとの「関係性」を、根本から再構築する、ということに他なりません。
これまでは、会社が個人のキャリアを預かり、面倒を見る、という関係でした。
これからは、会社は、「自社が、どんな仕事で、社会に価値を提供するのか」を、明確に示します。
そして、個人は、「自分は、どんな専門性で、その価値創造に貢献できるのか」を、主体的に発信していく。
そんな、プロフェッショナル同士の、対等なパートナーシップへと、関係性が変わっていくのです。
そのためには、学び直し、つまりリスキリングの機会を、会社がどう支援していくのか。
そして、働く一人ひとりが、いかに自律的に、自分のキャリアを設計していくのか。
この二つの歯車が噛み合ったとき、初めて、制度は血の通ったものとして機能し始めます。
ジョブ型人事制度は、日本企業にとって、大きな「変革のきっかけ」となり得ます。
しかし、その成功の鍵は、制度そのものの精巧さよりも、それを運用する「人と組織」が、どれだけ成熟した対話ができるかに、かかっているのです。
これからの人事戦略に必要な視点とは

ジョブ型人事制度とは、突き詰めれば、「人」ではなく、「仕事」を主語にして、組織を考える、という思想の転換です。
専門性の高い仕事には、それに見合うプロフェッショナルを。
そして、その成果には、正当な評価と報酬を。
その透明性が、この制度の核心にあります。
この、欧米では標準的とも言える考え方が、なぜ今、日本のビジネスシーンの大きなテーマとなっているのか。
それは、働き方の多様化や、グローバル化といった、もはや後戻りのできない、社会の大きな潮目の変化があるからです。
人事制度は、「入れ替える」のではなく、「仕立て直す」
しかし、ここで最も重要なのは、ジョブ型の導入を、単なる「制度の入れ替え」と考えてはいけない、ということです。
海外の流行を、そのまま自社に持ち込んでも、組織の文化や、働く人々の心と馴染まなければ、それはただの「借り物の服」となり、やがて機能不全に陥ります。
大切なのは、「自社の経営戦略にとって、今、本当に必要な人材は誰か」、「私たちの組織文化の、守るべき強みは何か」を、徹底的に見極めること。
そして、その目的に合わせて、既存の制度を丁寧に「仕立て直す」という、極めて戦略的な視点です。
鍵を握るのは、「企業と個人の、新しい対話」
これからの時代、企業と、働く個人との関係は、より対等なパートナーシップへと変わっていきます。
企業は、「自社がどんな価値を社会に提供し、そのために、どんな仕事をしてほしいのか」を、これまで以上に明確に、そして具体的に示す責任があります。
一方で、個人もまた、「自分はどんな専門性を持ち、その仕事を通じて、どう貢献できるのか」を、主体的に考え、発信していく力が求められます。
ジョブ型人事制度は、この、企業と個人との新しい「対話」を支える、非常に有効な土台となり得るのです。
これからの人事戦略を考える上で、私たちは、常に以下の視点を持ち続ける必要があります。
何よりもまず、人事制度を導入する「目的」を、経営の言葉で明確にすること。
次に、組織に存在する「仕事」の役割と責任を、誰の目にも見える形にすること。
そして、評価、報酬、育成という仕組みを、その仕事の価値と、一貫性を持って連動させること。
最後に、どんなに精巧な制度を作っても、その中心には常に「人」がいることを忘れないこと。
制度を機能させるのは、血の通った「対話」である、という原点です。
変化の激しい時代だからこそ、人事制度は、企業の競争力を左右する、最も重要な経営資源の一つです。
「人を、どう活かすか」。
この問いに、どれだけ真剣に向き合えるか。
その姿勢こそが、これからの時代に、社会から、そして働く人々から「選ばれる企業」であり続けられるかどうかの、分水嶺となるのではないでしょうか。



