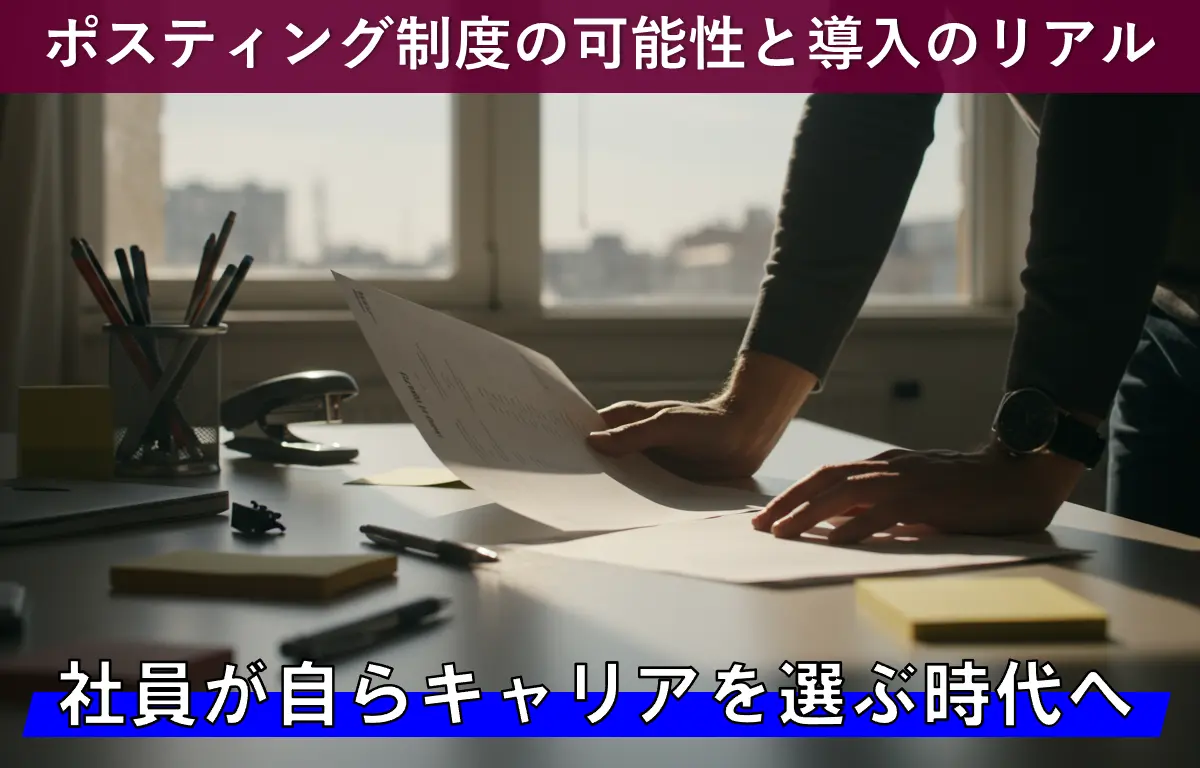
社員が自らキャリアを選ぶ時代へ、ポスティング制度の可能性と導入のリアル
最終更新日:2025/09/09
終身雇用は過去のもの?キャリア自律が求められる時代

かつて、日本の多くの企業では「終身雇用」と「年功序列」が人事制度の根幹をなしていました。
新卒で入社した会社に定年まで勤め上げ、年齢と共に役職と給与が上がっていく。
このモデルは、高度経済成長期の日本において、企業の安定的な成長と従業員の生活保障という両面で、非常に効果的に機能しました。
企業は従業員の忠誠心と引き換えに、長期的な視点での人材育成と安定した雇用を提供し、従業員は会社にキャリアを委ねることで、生活の安定と将来設計の描きやすさを手に入れていました。
しかし、バブル経済の崩壊、グローバル化の進展、そしてデジタル技術の急速な発展といった、激しい環境変化の波は、この日本的経営モデルの前提を大きく揺るがしました。
企業の成長が鈍化し、国際的な競争が激化する中で、もはや企業は、すべての従業員の雇用を無条件に保障し続ける体力も、その必要性も失いつつあります。
一方で、働く個人の価値観も大きく変化しました。
人生100年時代と言われるようになり、一つの会社だけでキャリアを終えるのではなく、自らの専門性やスキルを高め、より良い機会を求めて転職することや、副業・兼業に挑戦することも、もはや珍しいことではありません。
「会社にキャリアを委ねる」時代から、「自らの意思でキャリアを築く(キャリア自律)」時代へと、大きなパラダイムシフトが起こっているのです。
このような時代背景の中で、企業の人事戦略も大きな変革を迫られています。
画一的なキャリアパスを提示するだけでは、優秀な人材の意欲を引き出し、組織に定着させることは困難です。
従業員一人ひとりのキャリア志向や成長意欲に寄り添い、彼らが社内で新たな挑戦をできる機会を提供すること。
これこそが、変化の時代を生き抜くための、企業と個人の新たな関係性を築く鍵となります。
その具体的な施策の一つとして、今、大きな注目を集めているのが「ポスティング制度(社内公募制度)」です。
今回は、このポスティング制度がなぜ現代の企業にとって重要なのか、その導入がもたらすメリットと課題、そして制度を成功に導くための具体的なポイントまで、深く掘り下げて紹介していきます。
ポスティング制度(社内公募制度)とは何か

ポスティング制度(社内公募制度)とは、企業内で人材を必要としている部門が、その職務内容、求めるスキル、役職などを社内に公開し、希望する社員が自らの意思で応募できるようにする仕組みのことです。
従来の、会社主導による一方的な「異動」や「配置」とは異なり、社員の「自律的なキャリア選択」を尊重し、促進することを目的とした人事制度です。
この制度は、単に人材の欠員を補充するための手段にとどまりません。
企業にとっては、社内に埋もれている才能を発掘し、適材適所を実現するための戦略的なツールであり、社員にとっては、自らのキャリアパスを主体的に描き、新たなスキルや経験を獲得するための貴重な機会となります。
ポスティング制度の基本的な仕組み
ポスティング制度の運用方法は企業によって様々ですが、一般的には次のような流れで進められます。
【募集】
人材を必要とする部門が、人事部を通じて、または直接、社内イントラネットなどで募集要項を公開します。
募集要項には、部署名、職務内容、応募資格(必要なスキルや経験年数)、募集人数、選考プロセスなどが明記されます。
【応募】
募集要項を見た社員が、自身のキャリアプランや興味関心に基づき、自由に応募します。
多くの場合、応募の際には、直属の上司の承認が不要とされることが多く、これが社員の応募しやすさを高める重要なポイントとなります。
【選考】
募集部門と人事部が、応募者の経歴やスキル、志望動機などを基に、書類選考や面接を行います。
選考基準は、外部からの採用と同様に、公平かつ透明であることが求められます。
【決定・異動】
選考を通過した社員は、合格となり、正式な異動辞令が発令されます。
応募者と募集部門、そして現所属部門の間で、円滑な引き継ぎが行われるよう、人事部が調整役を担うこともあります。
FA(フリーエージェント)制度との違い
ポスティング制度と類似した制度に、「FA(フリーエージェント)制度」があります。
FA制度は、社員が自らのスキルや実績を社内に公開し、「自分はこのような仕事ができます」と宣言(FA宣言)するのに対し、興味を持った部門がその社員にアプローチ(スカウト)するという仕組みです。
ポスティング制度が「ポスト(職務)ありき」で、社員がそのポストに応募する「求人型」であるのに対し、FA制度は「人ありき」で、部門がその人に合ったポストを探す、あるいは創り出す「求職型」であるという点で、両者は異なります。
どちらの制度も、社員のキャリア自律を促すという目的は共通していますが、人材の流動化を促すアプローチに違いがあります。
なぜ、ポスティング制度が注目されるのか

ポスティング制度は、決して新しい仕組みではありません。
しかし、近年の労働環境の変化と、企業が抱える人材戦略上の課題を背景に、その重要性があらためて見直されています。
変化の時代における人材戦略の必要性
VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)と呼ばれる現代において、企業が競争優位性を維持するためには、事業環境の変化に迅速に対応できる、柔軟な組織体制と人材ポートフォリオが不可欠です。
新規事業の立ち上げや、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進など、従来にはなかった新しい専門性を持つ人材が、必要なタイミングで、必要な場所に配置されていることが、企業の成長を左右します。
ポスティング制度は、このような経営戦略上のニーズに対して、社内から迅速かつ的確に人材を発掘し、登用することを可能にします。
外部からの採用には時間もコストもかかりますが、社内公募であれば、企業文化や事業内容を既に理解している人材を、よりスムーズに配置することができるのです。
従業員のキャリア自律支援とエンゲージメント向上
現代のビジネスパーソン、特に若手層を中心に、「この会社で自分は成長できるのか」、「自分のキャリアは、自分で決めたい」という意識が非常に高まっています。
企業が一方的にキャリアパスを決める従来型の育成モデルは、もはや彼らのエンゲージEMENT(仕事に対する熱意や貢献意欲)を引き出すことが難しくなっています。
ポスティング制度は、社員に対して、社内にどのようなキャリアの選択肢があるのかを可視化し、自らの手で挑戦する機会を提供します。
このような「キャリア選択の機会」が与えられることは、社員の学習意欲や自己成長へのモチベーションを刺激し、「会社は自分のキャリアを応援してくれている」という信頼感を醸成します。
結果として、社員のエンゲージメントが高まり、組織全体の活性化につながるのです。
人材の定着とリテンション戦略
優秀な人材ほど、自己成長の機会や、より挑戦的な仕事ができる環境を求めて、社外に目を向けがちです。
特に、現在の部署での仕事にマンネリを感じていたり、キャリアの閉塞感を抱いていたりする場合、その傾向は顕著になります。
ポスティング制度は、このような社員に対して、社内にいながらにして新たな挑戦の場を提供することで、離職を防ぐための有効なリテンション(人材定着)戦略となり得ます。
転職という大きな決断を下す前に、「まずは社内で、自分の可能性を試してみよう」という選択肢を提示できることは、企業にとって、貴重な人材の流出を防ぐ上で、非常に大きな意味を持ちます。
ポスティング制度がもたらすメリット

ポスティング制度の導入は、企業と社員の双方にとって、多くのメリットをもたらします。
企業側(会社・人事)のメリット
適材適所の実現と人材の有効活用
人事部や経営層だけでは把握しきれていなかった、社員の潜在的な能力や隠れたキャリア志向を発掘することができます。
「営業部にいるAさんは、実はデータ分析のスキルに長けていた」、「管理部門のBさんは、新規事業の立ち上げに強い情熱を持っていた」といった、意欲と能力のある人材を、最適なポジションに配置することで、組織全体のパフォーマンスを最大化できます。
組織の活性化と新陳代謝の促進
部門の垣根を越えた人材の流動化は、組織に新しい風を吹き込みます。
異なる経験や視点を持つ人材が異動してくることで、既存の業務プロセスが見直されたり、新たなアイデアが生まれたりする「化学反応」が期待できます。
これにより、組織の硬直化を防ぎ、常に変化に対応できる、しなやかな組織文化が醸成されます。
採用コストの削減
新たな人材が必要になった際に、まず社内で候補者を探すことができるため、外部の採用市場に依存する必要性が低下します。
これにより、求人広告費や人材紹介会社への手数料といった、外部採用にかかるコストを大幅に削減することが可能です。
企業理念・文化の浸透
社員が自らの意思で、企業が戦略的に重要と位置付ける部門やプロジェクトに応募する、というプロセスを通じて、企業が目指す方向性や価値観が、社員一人ひとりに深く浸透していく効果も期待できます。
社員側のメリット
キャリア自律の実現
自らのキャリアを、会社任せにするのではなく、主体的に考え、選択する機会が得られます。
「自分は将来、どのような専門性を身につけたいのか」、「どのような経験を積みたいのか」という問いと向き合い、社内に用意された選択肢の中から、自らの手でキャリアを切り拓いていくことができます。
モチベーションとエンゲージメントの向上
自ら希望した職務に就くことで、仕事に対する当事者意識や責任感が高まります。
「やらされ仕事」ではなく、「自ら選んだ仕事」に取り組むことは、内発的なモチベーションを大きく向上させ、日々の業務への満足度と、会社へのエンゲージメントを高めることにつながります。
スキルアップと能力開発
現在の部署では得られない、新しいスキルや知識、経験を積む機会が得られます。
異動を通じて、これまでとは異なる視点や人脈を獲得することは、個人の市場価値を高め、将来のキャリアの可能性を大きく広げることになります。
社内人脈の形成
部門を越えて異動することで、社内の様々な部署の業務内容や、そこにいる人々への理解が深まります。
こうして形成された多様な社内ネットワークは、異動後も、円滑な業務遂行のための貴重な資産となります。
ポスティング制度導入のリアルと課題と乗り越え方

多くのメリットを持つポスティング制度ですが、その導入と運用は、決して簡単な道のりではありません。
制度を形骸化させず、真に機能させるためには、いくつかの現実的な課題と向き合い、適切な対策を講じる必要があります。
課題1:優秀な人材の流出と部門間の対立
ポスティング制度における最大の課題の一つが、異動元となる部門の抵抗です。
特に、優秀な人材、いわゆる「エース級」の社員が公募に応募した場合、現所属の上司や部門にとっては、大きな戦力ダウンとなります。
これにより、「優秀な人材ばかり引き抜かれる」と感じる部門と、「必要な人材を獲得したい」と考える募集部門との間で、対立が生じる可能性があります。
上司が、部下のキャリアを応援する気持ちよりも、自部門の業績維持を優先し、応募に対して非協力的になったり、引き留め工作を行ったりするケースも少なくありません。
乗り越えるためのポイント
経営トップからの強いメッセージ
ポスティング制度は、単なる人事異動の一手法ではなく、全社的な人材育成と組織活性化のための重要な経営戦略であることを、経営トップが繰り返し発信する必要があります。
「部門の都合よりも、社員の成長と全社の利益を優先する」という明確なメッセージが、管理職の意識改革を促します。
異動元部門へのインセンティブ
優秀な人材を育て、社内の他の部門へ送り出すことを、ポジティブに評価する仕組みを導入することも有効です。
例えば、部下をポスティング制度で異動させた実績を、管理職の人事評価項目に加えるなどが考えられます。
「部下を育てること=自部門に囲い込むこと」ではなく、「部下を育てること=全社に貢献できる人材にすること」という価値観への転換を促します。
計画的な人材育成とサクセッションプラン
エース級の人材が一人抜けただけで、業務が回らなくなるような状態は、組織として健全ではありません。
日頃から、業務の標準化や、複数担当者制の導入、そして次世代リーダーの計画的な育成(サクセッションプラン)に取り組むことで、特定の個人への依存度を下げ、人材の流動化に対する耐性を高めておく必要があります。
課題2:不合格者のモチベーション低下
公募に応募したものの、選考で不合格となった社員のモチベーションケアは、非常に重要な課題です。
「会社は自分を評価してくれなかった」、「今の職場に居づらくなった」と感じ、エンゲージメントが低下したり、最悪の場合、離職につながってしまったりするリスクがあります。
乗り越えるためのポイント
丁寧なフィードバック
不合格となった理由を、可能な限り具体的かつ丁寧に本人にフィードバックすることが不可欠です。
単に「今回はスキルがマッチしなかった」と伝えるだけでなく、「あなたの〇〇という強みは高く評価しているが、今回のポジションでは△△という経験がさらに必要だった。
今後、その経験を積むためには、□□といった方法がある」というように、本人の今後のキャリア形成に繋がるような、建設的なフィードバックを心がけます。
現職での成長機会の提供
応募という行動そのものが、本人の高い成長意欲の表れです。
その意欲を摘むのではなく、現所属の上司と人事部が連携し、本人が今の部署で新たな挑戦や学習ができるような機会(新しい役割の付与、研修への参加など)を提供することが重要です。
再挑戦の推奨
「今回は残念だったが、また次の機会にぜひ挑戦してほしい」というメッセージを伝え、一度の不合格がキャリアの終わりではないことを明確に示します。
課題3:制度の形骸化
募集されるポストが、魅力のない不人気部署の欠員補充ばかりであったり、実際には異動先が既に決まっている「出来レース」であったりすると、社員は制度そのものに不信感を抱き、応募しなくなってしまいます。
また、制度が十分に周知されていなかったり、応募のプロセスが煩雑であったりすることも、形骸化の原因となります。
乗り越えるためのポイント
魅力的なポストの提供
経営戦略上、重要度の高い新規事業や、花形とされる部署のポストも、積極的に公募の対象とすることが重要です。
「あの部署に行けるなら、挑戦してみたい」と社員が思えるような、魅力的なキャリア機会を提示することが、制度の活性化には不可欠です。
公平性と透明性の担保
選考プロセスを明確にし、応募者全員に公平な機会が与えられていることを示す必要があります。
選考基準や、どのような人物が選ばれたのかを、可能な範囲で公開することも、制度の透明性を高める上で有効です。
継続的な周知と改善
社内報やイントラネットなどを通じて、制度の目的や利用方法、そして制度を利用してキャリアを切り拓いた社員の成功事例などを、継続的に発信します。
また、利用者へのアンケートなどを通じて、制度の問題点を定期的に洗い出し、運用方法を改善していく姿勢も重要です。
企業と個人が共に成長する未来へ

ポスティング制度は、単なる人事制度の一つではありません。
それは、これからの時代の、企業と個人のあるべき関係性を映し出す鏡のようなものです。
企業は、社員を管理・支配の対象としてではなく、共に成長していくパートナーとして捉え、彼らの自律的なキャリア形成を積極的に支援する。
社員は、会社に依存するのではなく、自らのキャリアのオーナーシップを持ち、主体的に学び、挑戦し続ける。
ポスティング制度は、このような、自律した個人と、それを支えるプラットフォームとしての企業という、新しい関係性を構築するための、非常に有効な触媒となり得ます。
もちろん、その導入と運用には、今回紹介したような、多くの困難や抵抗が伴います。
しかし、その困難を乗り越え、制度を組織文化として根付かせることができたとき、そこには、変化を恐れず、常に新しい価値を創造し続ける、しなやかで強い組織の姿があるはずです。
そして、その組織の中では、社員一人ひとりが、自らのキャリアに誇りを持ち、活き活きと働いていることでしょう。
あなたの会社は、社員が自らのキャリアを、自らの手で選ぶことができる舞台を提供できているでしょうか。
この問いこそが、これからの時代の人事戦略を考える上での、最も重要な出発点となるのです。



