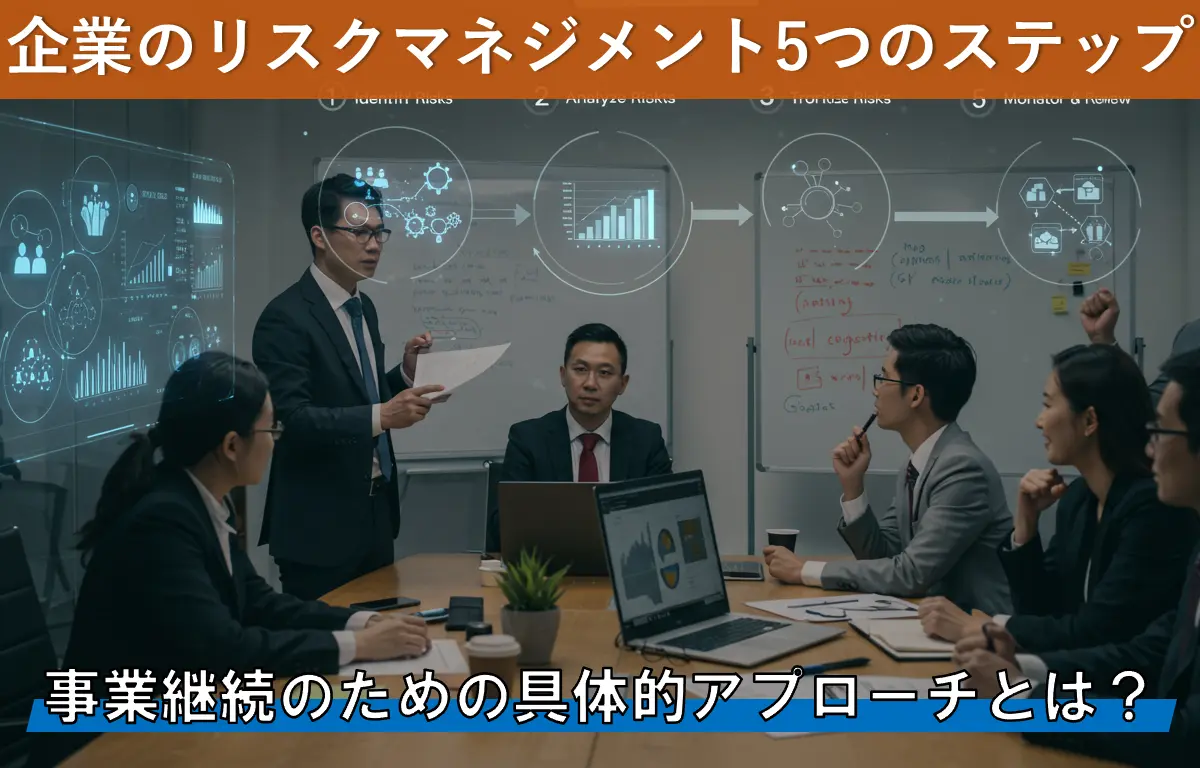
企業のリスクマネジメント5つのステップ|事業継続のための具体的アプローチとは?
最終更新日:2025/09/11
予測不能な時代を乗りこなす、企業の羅針盤「リスクマネジメント」

自然災害、パンデミック、サイバー攻撃、地政学的緊張、そして急激な市場の変化。
現代の企業経営は、まさに予測不能な荒波を航海する船に例えられます。
昨日までの常識が、今日には通用しなくなる。
そんな不確実性の高い時代において、座して嵐が過ぎ去るのを待つという選択肢は、もはや存在しません。
これまで多くの企業にとって、「リスクマネジメント」とは、事故や不祥事が起きた後の「事後処理」や、法務・コンプライアンス部門が担当する、どこか受け身で専門的な活動と捉えられていたかもしれません。
しかし、その認識は、企業の存続そのものが問われる現代において、根本から見直す必要があります。
現代におけるリスクマネジメントとは、単に損失を回避するための「守り」の活動ではありません。
それは、自社を取り巻く不確実性を体系的に理解し、脅威を最小化する一方で、リスクの裏側にある「機会」を的確に捉え、持続的な成長を遂げるための、極めて能動的で戦略的な「攻め」の経営基盤そのものなのです。
場当たり的な問題対応に終始する組織と、潜在的なリスクを事前に特定し、シナリオを描いて備える組織。
両者の間には、平時には見えにくい、しかし有事の際には企業の明暗を分ける、決定的で深淵な差が存在します。
強固なリスクマネジメント体制は、企業の体内に「免疫力」と「回復力(レジリエンス)」を宿らせ、予期せぬ危機に直面した際に、迅速かつ的確な意思決定を下すための、揺るぎない羅針盤となります。
では、この重要な羅針盤を、組織としていかにして手に入れ、活用していくべきなのでしょうか。
今回は、リスクマネジメントを単なるお題目で終わらせないために、その本質的な定義から、あらゆる企業が実践できる、5つのステップを、具体的なアクションと共に紹介します。
リスクマネジメントの本質、「危機管理」との決定的な違い

リスクマネジメントの具体的なステップに入る前に、その本質を正しく理解するために、しばしば混同されがちな「危機管理(クライシスマネジメント)」との違いを明確にしておく必要があります。
この二つは密接に関連していますが、その目的と時間軸において、決定的な違いがあります。
危機管理(クライシスマネジメント)とは
危機管理は、既に発生してしまった、あるいは発生が目前に迫っている危機的状況(クライシス)に対して、その被害や損害を最小限に食い止めるための「事後対応」に焦点を当てた活動です。
火事で言えば、既に上がった火を消す「消火活動」に相当します。
迅速な情報収集、的確な意思決定、ステークホルダーへの適切なコミュニケーションといった、緊急時の対応力がその中核をなします。
リスクマネジメントとは
一方、リスクマネジメントは、まだ発生していない「潜在的なリスク」を対象とし、それが現実の危機とならないように、あるいは、もし発生してもその影響が致命的なものとならないように、事前かつ継続的に手を打っていく「予防的活動」です。
火事の例で言えば、火災報知器を設置したり、燃えやすいものを近くに置かないようにしたり、避難経路を確認したりする「防火・防災活動」にあたります。
リスクマネジメントのプロセスが適切に機能していれば、多くの危機は未然に防がれ、危機管理が発動する場面そのものを減らすことができるのです。
つまり、リスクマネジメントは、危機管理の「上流工程」に位置づけられる、より長期的で包括的な経営活動と言えます。
優れたリスクマネジメント体制を構築することこそが、実効性のある危機管理の土台となるのです。
ステップ1:リスクの特定
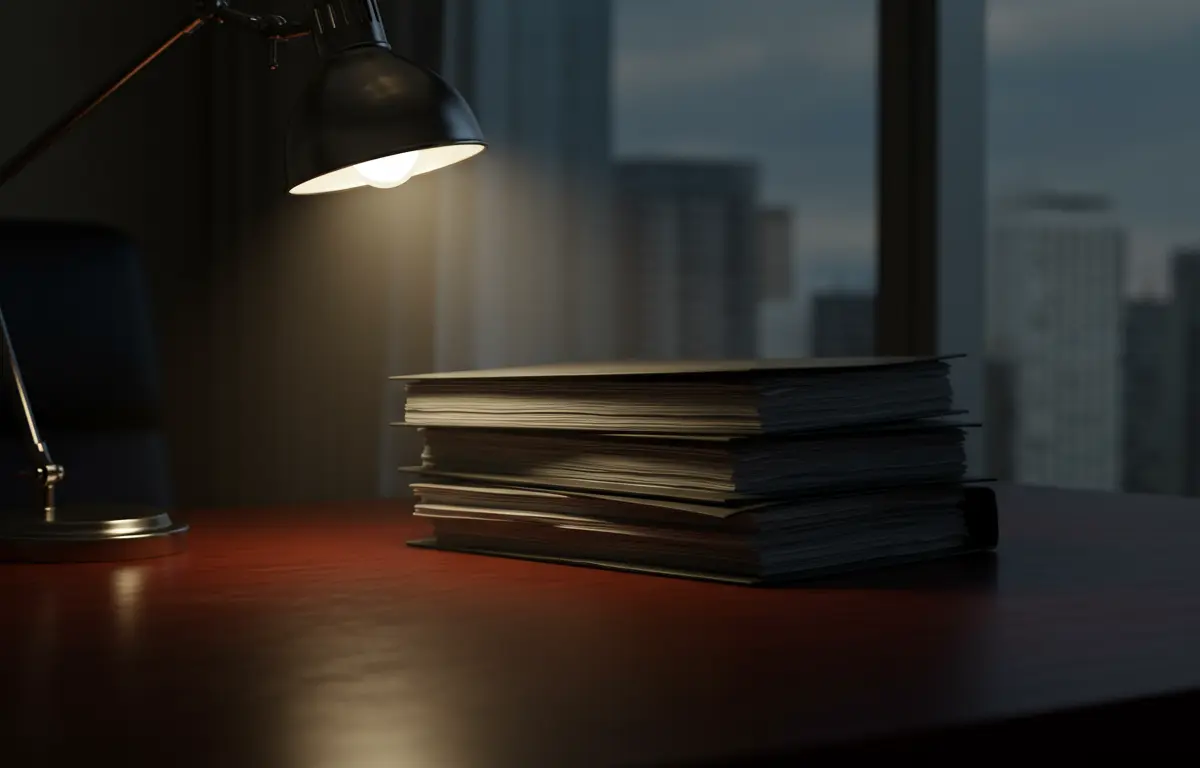
リスクマネジメントの全てのプロセスは、自社を取り巻く「リスクを漏れなく洗い出す」ことから始まります。
見えていないリスクに対して、備えることはできないからです。
このステップの目的は、完璧なリストを作ることよりも、組織全体で「どのようなリスクが存在しうるか」という感度を高め、潜在的な脅威を網羅的に可視化することにあります。
リスク特定のための具体的な手法
リスクを特定するためには、多様な視点からアプローチすることが重要です。
単一の手法に頼るのではなく、複数を組み合わせることで、より網羅性を高めることができます。
ブレインストーミングとワークショップ
各部署からメンバーを集め、新製品開発におけるリスクなどを例とする特定のテーマについて、自由にアイデアを出し合う手法です。
他者の意見が新たな気づきを促し、一人では思いつかなかったような多様なリスクを洗い出すことができます。
インタビューとアンケート
各部門の責任者や現場のキーパーソンに直接ヒアリングを行ったり、全社的にアンケートを実施したりすることで、それぞれの持ち場で認識されている具体的なリスクを収集します。
現場の生の声は、机上では見えてこない実践的なリスクを発見する上で非常に貴重です。
過去のインシデント分析
自社や同業他社で過去に発生した事故、クレーム、システム障害などの事例を分析します。
「なぜ、それは起きたのか」、「どのような影響があったのか」を掘り下げることで、再発の可能性があるリスクを特定します。
外部環境分析(PEST分析など)
自社ではコントロールできない、外部環境の変化に起因するリスクを捉えるためのフレームワークです。
Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の4つの観点から、自社に影響を与えうるマクロな変化を分析します。
リスクの分類とリスクレジスターの作成
洗い出したリスクは、その特性に応じて分類し、「リスクレジスター(リスク一覧表)」として文書化します。
これにより、リスクの全体像が可視化され、後の分析・評価プロセスがスムーズに進みます。
リスクの分類には、次のような切り口が考えられます。
戦略リスク
経営戦略の前提が崩れるリスク(例:市場ニーズの急変、競合の台頭、技術革新への乗り遅れ)。
財務リスク
資金繰りや収益性に影響を与えるリスク(例:為替変動、金利上昇、売掛金の貸し倒れ)。
オペレーショナルリスク
日々の業務プロセスに起因するリスク(例:システム障害、製造物責任、情報漏洩、人的ミス)。
コンプライアンスリスク
法令や社会規範に違反するリスク(例:不正会計、ハラスメント、環境規制違反)。
リスクレジスターには、特定された各リスクについて、その内容、発生しうる原因、影響を受ける部署などを記録していきます。
この文書が、組織のリスクマネジメント活動全体を通じて、中心的な役割を果たすことになります。
ステップ2:リスクの分析

リスクを特定した次のステップは、それらのリスクの「大きさ」を客観的に把握する「分析」のプロセスです。
すべてのリスクに同じように対応することは、リソースの観点から不可能です。
どのリスクに優先的に対処すべきかを見極めるため、各リスクの特性を深く理解する必要があります。
リスクの分析は、主に「発生可能性」と「影響度」という2つの軸で行われます。
発生可能性(Likelihood)の分析
「そのリスクが、将来的にどのくらいの確率で発生しうるか」を分析します。
完全に正確な確率を算出することは困難な場合が多いため、実務上は、定性的な尺度を用いて評価することが一般的です。
例えば、次のような段階で評価します。
高
過去に何度も発生しており、今後1年以内に発生する可能性が非常に高い。
中
過去に発生事例があり、今後数年以内に発生する可能性がある。
低
ほとんど発生したことはないが、理論的には発生しうる。
この評価は、過去のデータ、業界の統計、専門家の知見などを基に行います。
影響度(Impact)の分析
「そのリスクが、もし発生した場合に、事業にどの程度の損害や影響を与えるか」を分析します。
影響は、金銭的な損失だけでなく、信用の失墜、事業の停止、従業員の安全といった、多角的な視点から評価する必要があります。
こちらも、定性的な尺度で評価することが有効です。
甚大
事業の継続が困難になるレベルの致命的な影響。
大
経営に大きな打撃を与え、回復に長期間を要する影響。
中
一定の金銭的損失や信用の低下を招くが、事業継続は可能な影響。
小
影響は限定的で、通常の業務範囲内で対応可能なレベル。
特定したすべてのリスクについて、この「発生可能性」と「影響度」の2つの軸で分析を行い、その結果をリスクレジスターに追記していきます。
このプロセスを通じて、漠然としていたリスクの輪郭が、より明確なものとなってきます。
ステップ3:リスクの評価

リスクの分析によって、個々のリスクの「発生可能性」と「影響度」が明らかになりました。
次のステップである「評価」では、その分析結果を統合し、組織として「どのリスクを優先的に対処すべきか」を決定します。
この優先順位付けが、限られた経営資源を最も効果的に配分するための、重要な意思決定となります。
リスクマップ(リスクマトリックス)の活用
リスクの評価において、非常に強力なツールとなるのが「リスクマップ」です。
これは、縦軸に「影響度」、横軸に「発生可能性」をとったマトリックス図で、分析した各リスクをこの図の上にプロットしていきます。
このマップを作成することで、リスクの相対的な重要性が一目で可視化されます。
右上の領域(高リスク)
発生可能性も影響度も高い、最も警戒すべきリスク群。
組織として、最優先で具体的な対策を講じる必要があります。
左下の領域(低リスク)
発生可能性も影響度も低いリスク群。
必ずしも積極的な対策は必要なく、現状を監視し続ける、あるいはリスクとして受容するという判断が考えられます。
左上と右下の領域(中リスク)
発生可能性は低いが影響度は甚大(いわゆるブラックスワン型のリスク)なものや、影響は小さいが発生頻度は高いものなどが、ここに位置します。
これらのリスクに対しては、コストと効果のバランスを考慮しながら、対策の要否を慎重に検討する必要があります。
リスクアペタイト(許容度)の設定
リスクマップ上で優先順位を可視化した上で、最終的に「どのレベルのリスクまでなら、対策を講じずに受け入れるか」という基準、すなわち「リスクアペタイト(Risk Appetite)」を組織として明確にする必要があります。
リスクアペタイトは、企業の経営体力、事業戦略、そして企業文化によって異なります。
例えば、安定性を重視する企業はリスクアペタイトが低く、わずかなリスクでも積極的に対策を講じるでしょう。
一方で、成長を追求するベンチャー企業は、一定のリスクを取ることを許容する、高いリスクアペタイトを持つかもしれません。
この基準を明確にすることで、「このリスクには対策が必要」、「このリスクは許容範囲内」といった、一貫性のある意思決定が可能になります。
この評価プロセスを経て、組織が取り組むべき優先課題が、具体的かつ明確な形で定義されるのです。
ステップ4:リスクへの対応

リスクの評価によって、優先的に対処すべきリスクが明確になりました。
このステップでは、それらのリスクに対して、具体的にどのような「打ち手」を講じるかを決定し、実行計画に落とし込みます。
リスクへの対応策は、一般的に4つのカテゴリーに分類されます。
どの対応策を選択するかは、リスクの性質や、対策にかかるコストと得られる効果のバランスを考慮して、慎重に判断する必要があります。
リスクコントロール(リスクの制御)
リスクそのものの発生可能性や影響度を低減させるための、積極的なアプローチです。
リスクの回避(Avoidance)
リスクの原因となる活動そのものを中止、あるいは変更することで、リスクを根本的に取り除く対応策です。
例えば、政治的に不安定な国での事業展開を中止する、あるいは、非常に危険性の高い化学物質の使用をやめ、より安全な代替物質に切り替える、といった判断がこれにあたります。
最も確実な対策ですが、事業機会の損失を伴う可能性もあります。
リスクの低減(Mitigation/Reduction)
リスクの発生可能性を下げる、あるいは、もし発生した場合の影響度を軽減するための対策を講じるアプローチです。
これは、最も一般的に取られるリスク対応策です。
例えば、情報漏洩リスクに対して、セキュリティシステムを強化したり、従業員教育を実施したりする(発生可能性の低減)。
また、火災リスクに対して、スプリンクラー設備を導入する(影響度の低減)、といった対策が挙げられます。
リスクファイナンシング(リスクの財務的処理)
リスクそのものを減らすのではなく、発生した場合の金銭的な損失に備えるアプローチです。
リスクの移転(Transfer)
リスクによって生じる経済的損失の負担を、保険会社や取引先など、第三者に移転する手法です。
損害保険への加入がその典型例です。
また、専門性の高い業務を外部委託することで、それに伴うリスク(例:情報システムの運用リスク)を委託先に移転することも、この一種と考えられます。
ただし、企業の評判に関わるリスクなど、移転できないリスクも存在します。
リスクの保有(Retention/Acceptance)
リスクを認識した上で、特段の対策を講じず、そのリスクを受け入れるという判断です。
これは、リスク評価の結果、影響が軽微であると判断された場合や、対策にかかるコストが、想定される損失を大幅に上回る場合に選択されます。
リスクを「保有」すると決定した場合は、万が一発生した際の損失に備えて、引当金を積むなどの財務的な準備をしておくことが賢明です。
これらの選択肢の中から、各リスクに対して最適な対応策を決定し、「誰が」、「いつまでに」、「何をするか」を明確にした具体的な実行計画を作成します。
この計画が、リスクマネジメントを絵に描いた餅で終わらせないための、具体的なアクションプランとなります。
ステップ5:モニタリングとレビュー

リスクマネジメントは、一度計画を立てれば終わり、という性質のものではありません。
企業を取り巻く環境は常に変化し、新たなリスクが生まれ、既存のリスクの性質も変わっていきます。
最後のステップである「モニタリングとレビュー」は、これまでのプロセスが有効に機能しているかを確認し、変化に対応して継続的に改善していくための、極めて重要な循環的な活動です。
継続的な監視(モニタリング)の重要性
モニタリングは、リスクマネジメントのプロセスが、計画通りに、そして効果的に実行されているかを常に監視する活動です。
具体的には、次のような点を確認します。
リスク対応策の進捗状況
ステップ4で定めた実行計画が、担当者によって計画通りに進められているか。
遅延や問題は発生していないか。
リスクの変化の兆候
リスクレジスターに記載されたリスクの発生可能性や影響度に、変化の兆しはないか。
例えば、特定の顧客からのクレームが増加している、あるいは、特定の部品の納期遅延が頻発しているといった情報は、より大きな問題の前兆である可能性があります。
新たなリスクの出現
外部環境の変化(新たな法規制の導入、競合の新技術開発など)や、内部環境の変化(新規事業の開始、組織変更など)によって、これまで認識されていなかった新しいリスクが発生していないかを常に監視します。
これらのモニタリングは、リスク管理部門だけでなく、各現場部門が日常業務の中でアンテナを高く張ることが、効果を高める上で不可欠です。
定期的な見直し(レビュー)と改善サイクル
レビューは、これまでのリスクマネジメントの枠組み全体を、定期的に見直し、評価する活動です。
通常、年に一度、あるいは半期に一度といったタイミングで、経営層も参加して行われます。
レビューでは、次のような点が議論されます。
リスクマネジメント方針の妥当性
現在のリスクマネジメントの方針や、設定されているリスクアペタイトは、変化した経営環境に照らして、今もなお適切か。
リスク評価の再評価
リスクマップ全体を見直し、各リスクの優先順位に変動はないか。
新たに対応が必要となるリスクはないか。
プロセス全体の有効性
リスクの特定からモニタリングまでの一連のプロセスは、効果的に機能しているか。
改善すべき点はないか。
このレビューの結果を受けて、リスクマネジメントの方針や計画を更新し、新たなアクションプランに繋げていきます。
この「モニタリングとレビュー」を通じて、特定から対応までの一連のプロセスを継続的に循環させる、いわゆるPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回すこと。
これこそが、リスクマネジメントを形骸化させず、変化に対応し続ける「生きた仕組み」として組織に根付かせるための、唯一の道筋なのです。
リスクマネジメントは、未来を創造する「攻め」の経営戦略である

今回は、企業経営における羅針盤とも言うべき、リスクマネジメントの体系的なプロセスを、5つの具体的なステップに沿って紹介してきました。
潜在的なリスクを網羅的に「特定」し、その性質を客観的に「分析」する。
そして、組織としての優先順位を「評価」し、最適な対策を「実行」する。
最後に、そのプロセス全体を継続的に「見直し」、変化に対応し続ける。
この一連のサイクルは、業種や企業規模を問わず、あらゆる組織が持続的な成長を遂げる上で、不可欠な経営のフレームワークです。
これまでの内容を通じて、現代におけるリスクマネジメントが、単に不祥事を防いだり、損失を回避したりするだけの消極的な「守り」の活動ではないことを、ご理解いただけたのではないでしょうか。
自社を取り巻くリスクを深く理解するプロセスは、裏を返せば、自社の「強み」と「弱み」、そして外部環境にある「機会」と「脅威」を、解像度高く再認識するプロセスに他なりません。
リスクシナリオを検討する中で、既存事業の脆弱性が明らかになるかもしれません。
しかし同時に、これまで見過ごされていた新たな事業機会や、競合がまだ気づいていない市場のニーズを発見することにも繋がるのです。
強固なリスクマネジメント体制は、組織に「レジリエンス(回復力)」をもたらします。
それは、予期せぬ危機に直面しても、致命的なダメージを回避し、迅速に立ち直る力です。
そして、このレジリエンスこそが、企業が不確実性の高い時代において、失敗を恐れずに新しい挑戦を続けるための、心理的な安全基盤となります。
リスクマネジメントを、コストセンターと見なすか、未来への戦略的投資と見なすか。
この認識の違いが、これからの企業の成長角度を大きく左右します。
予測不能な未来をただ恐れるのではなく、その不確実性の中から新たな価値を創造していく。
それこそが、リスクマネジメントの本質であり、未来を生き抜くすべての企業に求められる、真に「攻め」の経営戦略と言えるのではないでしょうか。



