
ジブリ風AI画像は著作権侵害?ビジネス利用の法的リスクを紹介
最終更新日:2025/09/09
新たな表現の奔流と、その影に潜む法的課題
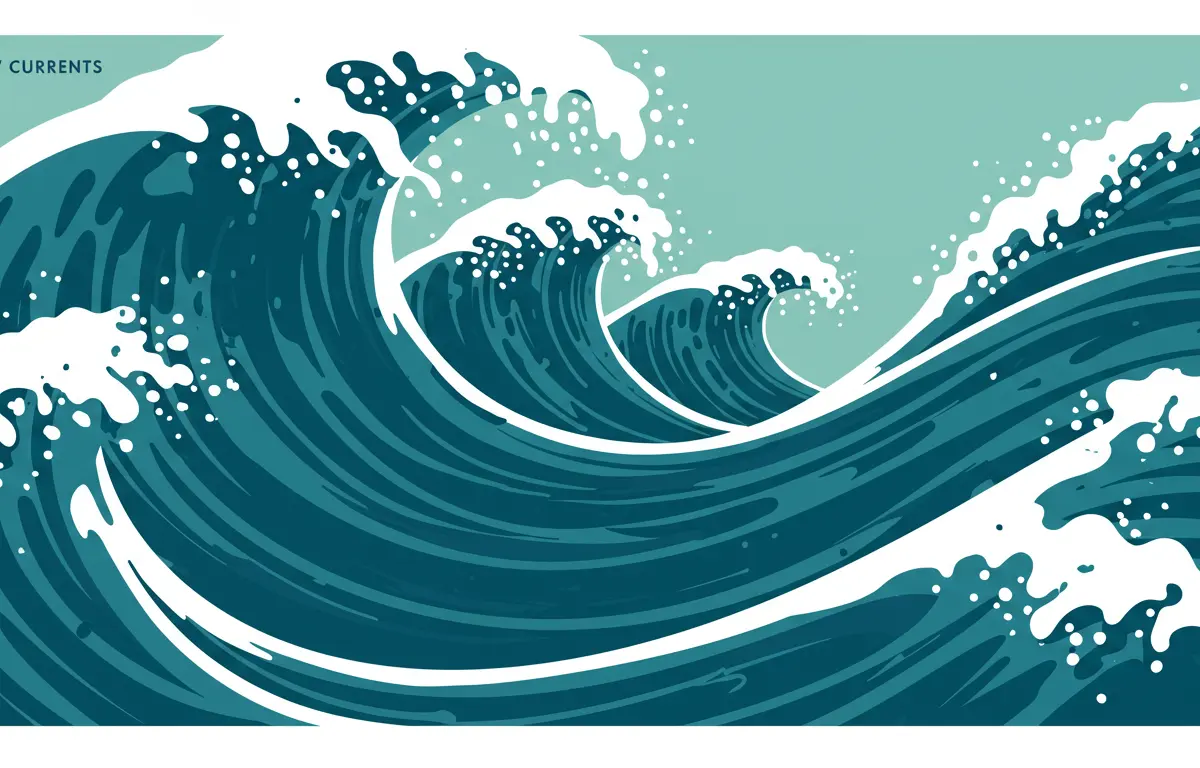
ノスタルジックで温かみのある独特のタッチ、息をのむほど美しい背景美術、そして愛すべきキャラクターたち。
スタジオジブリが世に送り出してきたアニメーション作品は、世代と国境を越えて多くの人々の心を魅了し続けています。
その影響力は計り知れず、「ジブリ風」という言葉は、もはや一つの確立されたアートスタイルとして認識されています。
近年、この「ジブリ風」の画風を、誰でも手軽に再現できる画像生成AIが大きな注目を集めています。
SNSのタイムラインをスクロールすれば、まるでジブリ映画のワンシーンのような、幻想的で美しいAI画像を目にする機会も少なくないでしょう。
クリエイターやデザイナーにとっては、自らのアイデアを視覚化するための強力なツールとなり、一般のユーザーにとっては、創造の喜びを手軽に体験できる新しいエンターテインメントとなっています。
しかし、この新たな表現の奔流は、その影に複雑な法的・倫理的な課題を潜ませています。
その核心にあるのが、「著作権」の問題です。
「特定のクリエイターの画風を模倣したAI画像を生成し、公開することは、著作権侵害にあたらないのか?」
「AIが生成した『ジブリ風』の画像に、著作権は発生するのか?」
「ビジネスシーンで、これらの画像を安心して利用することはできるのか?」
これらの問いは、テクノロジーの進化が、既存の法制度やクリエイターの権利と、どのように向き合っていくべきかという、現代社会が直面する大きな課題を映し出しています。
特に、広告やマーケティング、コンテンツ制作などの実務に携わるビジネスパーソンにとって、この問題は決して他人事ではありません。
安易な利用が、意図せずして企業の信用を損なう法的紛争に発展するリスクも、十分に考えられるからです。
今回は、この「ジブリ風」AI画像と著作権をめぐる問題を、現在の日本の法律に照らし掘り下げて紹介します。
著作権法の基本と「画風」の法的保護

「ジブリ風」AI画像の問題を理解するためには、まず、その根幹にある著作権法が、何をどのように保護しているのか、その基本原則を正しく理解する必要があります。
特に重要なのが、「アイデア」と「表現」の区別、そして「画風」が法的にどのように扱われるか、という点です。
著作権法が保護するものは「表現」であって「アイデア」ではない
著作権法は、文化的な創作物を保護し、創作者(著作者)の権利を守るための法律です。
しかし、この法律が保護するのは、具体的な「表現」であって、その根底にある「アイデア(思想又は感情)」そのものではありません。
これは「アイデア・表現二分論」と呼ばれ、著作権法の最も基本的な原則の一つです。
(具体例)
・アイデア:「少年が冒険を通じて成長する物語」
・表現:「『ONE PIECE』のルフィが仲間と共に冒険する具体的なストーリーや描写」
この場合、著作権で保護されるのは、後者の具体的な「表現」です。
したがって、「少年が冒険を通じて成長する」というアイデア自体は誰でも自由に利用でき、同じアイデアを基に全く新しい物語を創作しても、著作権侵害にはなりません。
もしアイデア自体を独占させてしまうと、後から創作する人々の自由な発想が妨げられ、文化の発展が阻害されてしまうためです。
「画風」や「作風」はアイデアか、表現か
では、「ジブリ風」に代表されるような、特定のクリエイターの「画風」や「作風」は、著作権法上、どのように扱われるのでしょうか。
結論から言うと、現在の日本の裁判例では、「画風」や「作風」といった、抽象的なスタイルは、「アイデア」の範疇に属するものと解釈されており、原則として著作権による保護の対象にはならない、と考えられています。
例えば、ある画家が、太い輪郭線と鮮やかな色彩で人物を描く、という独特のスタイルを持っていたとしても、他の画家が、そのスタイルを模倣して、全く別の人物画を描くことは、原則として著作権侵害にはあたりません。
そのスタイルは、あくまで創作上の「アイデア」や「手法」であり、具体的な「表現」そのものではない、と判断されるためです。
この考え方を「ジブリ風」に当てはめると、「柔らかい描線、水彩画のような背景、ノスタルジックな雰囲気」といった、抽象的な「ジブリらしさ」を構成する画風自体は、著作権の保護対象ではない、ということになります。
したがって、AIを用いて、この「ジブリ風」というスタイルを模倣した、全く新しいオリジナルの画像を生成すること自体は、直ちに著作権侵害となるとは言えない、というのが現在の法的な考え方の出発点となります。
しかし、問題はそう単純ではありません。
AIが生成した画像が、単に「画風が似ている」というレベルを超えて、スタジオジブリの特定の作品に登場するキャラクターや背景と酷似している場合には、話が大きく変わってきます。
AIによる画像生成と著作権侵害の判断基準

「ジブリ風」という画風の模倣自体は、直ちに著作権侵害とはなりません。
しかし、AIによる画像生成プロセスと、その生成結果(アウトプット)によっては、著作権侵害が成立する可能性が十分にあります。
ここでは、どのような場合に著作権侵害が問題となるのか、その判断基準を「AIの学習(インプット)」と「生成(アウトプット)」の二つのフェーズに分けて見ていきます。
【フェーズ1】AIの学習(インプット)段階における著作権
画像生成AIは、その能力を獲得するために、インターネット上などに存在する膨大な量の画像データを「学習」します。
この学習データの中に、スタジオジブリの作品画像など、著作権で保護された画像が含まれている場合、その学習行為自体が、著作権(複製権)の侵害にあたるのではないか、という論点があります。
【原則】著作権法第30条の4による適法化
この点について、日本の著作権法は、2018年の改正で、AI開発を促進するための非常に先進的な規定を設けています。
それが、著作権法第30条の4です。
この条文は、AI開発などの「情報解析」を目的とする場合には、原則として、著作権者の許諾なく、著作物を利用(複製など)することができる、と定めています。
つまり、画像生成AIが、その能力を高めるために、インターネット上にある「ジブリの画像」を学習データとして収集し、解析(学習)することは、この条文によって適法とされる可能性が高いのです。
これは、日本のAI開発における国際競争力を高めるための、政策的な判断に基づいています。
【例外】「思想又は感情の享受を目的とする場合」
ただし、この第30条の4には、但し書きがあります。
それは、その著作物の利用が、「思想又は感情の享受を目的とする場合」には、適用されない、というものです。
例えば、「ジリ風の画像を学習させたAI」と称して、実質的にはジブリの海賊版画像を大量にデータベース化し、ユーザーに閲覧させるようなサービスは、AI開発のためではなく、単に画像鑑賞(享受)を目的としていると判断され、違法となる可能性があります。
【フェーズ2】AIによる生成(アウトプアウト)段階における著作権
AIの学習段階が適法であったとしても、AIが生成した画像が、既存の著作物と似ている場合には、著作権侵害(複製権または翻案権の侵害)が問題となります。
ここが、ユーザーにとって最も注意すべきポイントです。
【判断基準】「依拠性」と「類似性」
AI生成画像が、特定の著作権者の権利を侵害しているかどうかは、最終的に、以下の二つの要件を満たすかどうかで判断されます。
依拠性
依拠性とは、既存の著作物(元の作品)を知っていて、それに基づいて創作した、という関係を指します。
画像生成AIの場合、ユーザーが「〇〇(特定のキャラクター名)をジブリ風に」といったプロンプト(指示)を入力した場合、その特定のキャラクターの画像を参考にして生成しているため、原則として依拠性があると認められやすくなります。
また、AIの学習データに元の作品が含まれている場合も、依拠性が認められる一因となり得ます。
類似性
類似性とは、AIが生成した画像が、元の作品の「表現形式上の本質的な特徴」を、直接感得できる(見てすぐにそれと分かる)ほど似ているかどうか、という基準です。
単に「画風が似ている」というだけでは、類似性があるとは言えません。
キャラクターの具体的なデザイン(顔のパーツ、髪型、服装など)や、背景の構図、特徴的な建物のデザインなどが、誰が見ても元の作品そのもの、あるいはその「パクリ」だと認識できるレベルで酷似している場合に、類似性が認められます。
著作権侵害となる可能性が高いケース
上記の「依拠性」と「類似性」の両方が認められた場合、著作権侵害となる可能性が非常に高くなります。
(具体例)
・「となりのトトロ」の「トトロ」や「ネコバス」を、AIに酷似した形で描かせ、その画像をSNSのアイコンに使用する。
・「千と千尋の神隠し」の「油屋」の建物を、AIに詳細に再現させ、その画像を広告デザインの一部として無断で利用する。
このような利用は、元の作品の複製権(そっくりそのままコピーした場合)や、翻案権(元の作品に修正や増減を加えて、新たな作品を創作した場合)を侵害する行為と見なされるリスクがあります。
AI生成物の著作権は誰のものか?

もう一つの大きな論点が、「AIが生成した画像に、そもそも著作権は発生するのか?」、そして「発生するとしたら、それは誰に帰属するのか?」という問題です。
これもまた、現在の法制度が直面する新しい課題です。
AIは「著作者」になれるのか?
日本の著作権法では、「著作者」を「著作物を創作する者(人)」と定義しています(第2条第1項第2号)。
現在の法解釈では、AI(人工知能)そのものは「人」ではないため、「著作者」になることはできません。
したがって、AIが自律的に、完全に自動で生成した画像には、著作者が存在せず、著作権も発生しない、というのが基本的な考え方です。
「人の創作的寄与」が認められるかどうかが鍵
では、人間がAIを「道具」として利用して画像を生成した場合はどうでしょうか。
この場合、著作権が発生するかどうかは、「人の創作的寄与」があったかどうか、で判断されます。
つまり、人間が、自らの「思想又は感情」を創作的に表現するための「道具」としてAIを使い、その生成プロセスに、人間による創作的な意図や工夫が具体的に反映されていると認められる場合に、その人間を著作者として、生成物に著作権が発生すると考えられています。
著作権が発生する可能性が高いケース
・プロンプト(指示)の工夫:生成したい画像イメージを具体化するために、何段階にもわたって、独創的なプロンプトを試行錯誤し、作り込んでいく場合。
・生成画像の選択・修正:AIが生成した多数の候補の中から、特定の画像を選択し、さらに画像編集ソフトなどを用いて、大幅な加筆・修正を加える場合。
このような場合は、人間の「創作的な選択や修正の行為」が認められ、著作権が発生する可能性が高まります。
その画像の著作者は、AIではなく、AIを操作した人間ということになります。
著作権が発生しない可能性が高いケース
・単純なプロンプトの入力:単に「ジブリ風の風景」といった、ありふれた短い単語を入力しただけで、AIが自動的に生成した画像を、そのまま利用する場合。
この場合は、人間の創作的な寄与がほとんどなく、実質的にAIが自律的に生成したものと変わらないため、著作権は発生しない可能性が高いと考えられます。
このような画像は、「パブリックドメイン(社会の共有財産)」となり、誰でも自由に利用できることになります。
ビジネス利用における法的リスクと実務対応

これまで見てきたように、「ジブリ風」AI画像の利用には、著作権侵害のリスクと、そもそも著作物として保護されない可能性という、二つの側面があります。
これらの法的リスクを踏まえ、ビジネスパーソンが実務でAI生成画像を利用する際には、どのような点に注意すべきでしょうか。
【リスク1】著作権侵害による損害賠償
AIが生成した画像が、スタジオジブリなどの第三者が持つ著作権(複製権・翻案権)を侵害していると判断された場合、企業は、著作権者から、次のような請求を受ける可能性があります。
・利用の差止請求:画像の利用を直ちに停止するよう求められます。
・損害賠償請求:著作権者に与えた損害を、金銭で賠償するよう求められます。
・不当利得返還請求:画像の利用によって得た利益を返還するよう求められます。
・名誉回復措置請求:謝罪広告の掲載などを求められる場合があります。
これらの法的な請求は、企業の経済的な損失だけでなく、ブランドイメージや社会的信用の失墜といった、計り知れないダメージにつながる可能性があります。
【リスク2】権利関係の不安定さ
仮に、利用しているAI生成画像が、第三者の著作権を侵害していなかったとしても、その画像自体に著作権が発生していない(パブリックドメインである)可能性があります。
この場合、自社が広告などで利用している画像を、競合他社が完全に同じように、あるいは少し改変して、自社の広告に無断で利用したとしても、著作権侵害を主張して、その利用を差し止めることができません。
自社のブランディング上、独自性が重要となるような画像については、権利関係が不安定なAI生成画像を利用すること自体が、ビジネス上のリスクとなり得ます。
ビジネスパーソンが取るべき実務対応
これらのリスクを回避し、AI生成画像を安全に活用するために、次の点を強く推奨します。
利用するAIサービスの利用規約を確認する
まず、利用する画像生成AIサービスの利用規約を熟読し、次の点を確認することが不可欠です。
・生成した画像の商用利用は許可されているか?
・生成した画像の著作権は、誰に帰属すると定められているか?
・生成した画像が、第三者の権利を侵害した場合の、AI開発企業の免責条項や補償の範囲はどうなっているか?
特定の作品やキャラクターを想起させるプロンプトを避ける
著作権侵害のリスクを低減させるための、最も基本的かつ重要な対策は、プロンプトに、既存の著作物(作品名、キャラクター名、作家名など)を直接的に指定する言葉を入力しないことです。
「ジブリ風」という言葉も、依拠性を認定される一因となり得るため、商用利用を前提とする場合は、「ノスタルジックなアニメ風」、「水彩画調の美しい風景」といった、より抽象的で一般的な言葉に置き換えるべきです。
生成された画像をそのまま利用しない
生成された画像を、自社のオリジナリティある著作物として権利主張したい場合は、それを素材として捉え、デザイナーなどが大幅な加筆・修正を加えるプロセスを挟むことが重要です。
これにより、「人の創作的寄与」が明確になり、著作物として認められる可能性が高まります。
オリジナリティと権利のクリーンさを重視するなら
企業の根幹となるロゴマークや、長期的に使用する主要な広告ビジュアルなど、特にオリジナリティと権利の安定性が求められるクリエイティブについては、現時点では、AI生成画像に全面的に依存するのではなく、プロのクリエイターに依頼して、完全にオリジナルな作品を制作することが、最も安全かつ賢明な選択と言えるでしょう。
技術との健全な共存を目指して

画像生成AIは、私たちの創造性を刺激し、ビジネスに新たな可能性をもたらす、非常にパワフルなツールです。
「ジブリ風」という多くの人々を魅了するスタイルを、誰もが探求できるようになったことは、その象徴的な事例と言えるでしょう。
しかし、その利用にあたっては、新たなテクノロジーが、既存の法的・倫理的な枠組みと、いかにして調和していくかという、慎重な視点が不可欠です。
特に、スタジオジブリをはじめとするクリエイターたちが、長年にわたって築き上げてきた独創的な世界観と、その根底にある著作権という権利に対して、私たちは最大限の敬意を払わなければなりません。
AIという「魔法の杖」を手にしたからといって、他者の創造の成果を、無断で、あるいは安易に利用することが許されるわけではないのです。
本稿で紹介した著作権法の知識は、AIと共存していく未来において、ビジネスパーソンが自らと自社を守るための、必須のリテラシーです。
技術の進化を恐れるのではなく、その仕組みとリスクを正しく理解し、ルールを守って賢く活用すること。
その姿勢こそが、クリエイティブ産業の健全な発展を支え、ひいては私たち自身のビジネスを、より豊かで持続可能なものへと導いていくはずです。



